milsilバックナンバー
2025年

2025年の夏、福井県の水月湖で「年縞」が掘削されました。年縞は、タイムカプセルのように過去を保存している縞模様の堆積物です。水月湖の湖底に眠る年縞は約7万年分。これほどの年縞は世界にも例がありません。
今回の特集では、「奇跡の湖」とよばれる水月湖の年縞の価値、その実物を展示する福井県年縞博物館、世界の年縞を調べてわかってきたこと、そして、過去の気候と文明からの考察などを、まさに掘削の現場から紹介しています。
今月の表紙
画像提供:福井県年縞博物館(年縞)、水月湖プロジェクト(葉化石)、立命館大学・中川毅「暴れる気候」プロジェクトチーム(撮影・竹田武史、2025年の掘削現場写真)
| 【特集】 | 湖底のしましま「年縞」と気候変動 | 3 |
| 湖底の縞模様 「年縞」は何を記録しているのか | 4 | |
| 世界一細長い博物館の7万個のタイムカプセル | 6 | |
| 「年代のものさし」をつくる方法 | 9 | |
| 「暴れる気候」と文明の衰退 | 12 | |
| 「暴れない気候」と文明の始まり | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 難治性のかゆみにかかわるタンパク質の役割を解明!
―セマフォリン3Aの働きに迫る─ |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #105 DNAを組み立てよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第16回 | 森のネズミとクリーンな共生をする
オオヤドリカニムシ |
26 |
| かはくレポート | 特別展「氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~」
過酷な気候を生きた人類や動物たちの足跡から学ぶ |
30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

太陽や夜空の星(恒星)の輝きは永遠ではありません。星もいつかは死を迎えるのです。一方で、宇宙では、新たな星が常にどこかで誕生しています。
星の誕生と死は、私たち生命ともつながりがあります。
今回の特集では、星がいかにして誕生し、死を迎えるのか、そして星の誕生と死がどのように私たち生命とつながっているのかを最新の天文学の研究に基づいて紹介しました。
今月の表紙
画像提供:
(上)[Science]NASA, ESA, CSA, STScI[Image Processing]Joseph DePasquale (STScI), Alyssa Pagan (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)
(下)NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
| 【特集】 | 星たちの「誕生」と「死」 | 3 |
| 多様な元素をつくり出した星たちの物語 | 4 | |
| 「暗黒星雲」の中で生命の素材がつくられた | 6 | |
| 星のゆりかご「オリオン大星雲」
はどのようにして生まれたのか |
9 | |
| 太陽の未来の姿 | 12 | |
| 重量級の恒星は
「超新星爆発」を起こして生涯を終える |
15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | ―稲作の起源に遺伝子の変異から迫る─
イネの種子が穂から落ちないのは遺伝子変異のおかげ |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #104 サイフォンの原理を使ってみよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第15 回 | アリの社会に見る、仁義なき寄生戦略
アリの巣を侵略するトゲアリ |
26 |
| かはくレポート | プレスリリース「ウグイスの谷渡り鳴きの新仮説」に寄せて
ウグイスは一夫多妻のおもしろい鳥 |
30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

今月の表紙は、地球内部をイメージしたイラストです。
そして特集は「宇宙より遠い!? 地球の内部構造に迫る」です。
地球は、半径約6400 km の球体で、その内部は大きく、①地殻、②マントル、③コア(核)の3 つの層で構成されています。
マントルは、実際はさらにいくつかの層構造をもっています。コアは、中心に近いほうを内核、マントルに近いほうを外核といいます。
地球は内部にいくほど高温、高圧になり、中心は約5000℃、364万気圧と考えられています。地殻、マントル、内核は固体で、外核は液体です。
今回の特集では、地殻を地質学的に調べたり、地震波を観測したり、内部の高温・高圧状態を実験室でつくり出したりするなど、多彩な研究方法を紹介しています。全体監修は廣瀬 敬(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)によります。
今月の表紙
画像提供:Johan Swanepoel /Shutterstock.com
| 【特集】 | 宇宙より遠い!? 地球の内部構造に迫る | 3 |
| 地球の内部構造はどこまでわかったか | 4 | |
| 大型超高圧装置で探るマントルの構造と物質 | 6 | |
| 地球の中心部"コア"は何でできているか | 9 | |
| 地震波形解析で地球内部を探る | 12 | |
| 海洋科学掘削の歴史とこれから | 15 | |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 南極に設置した大型大気レーダー「PANSY」で
高度10~100 kmの中層大気の特徴を解明 |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #103 固体?液体?不思議な物質を観察しよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第14回 | 光合成をやめ、菌類に頼って生きる!?
モイワランとサイハイラン |
26 |
| かはくレポート | 特別展「古代DNA -日本人のきた道-」
21世紀の日本人起源論/篠田 謙一 (国立科学博物館長) |
30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
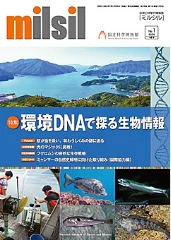
見慣れない魚が釣れるようになった、よく見かけていた虫がいなくなったなど、身近な自然の異変を心配する声が聞こえてきます。
今号の特集では、環境中に含まれる生物のDNAから、そこに生息する生物種を把握することを可能にした環境DNA調査を取り上げました。
これまでは捕獲したり、実際に潜ったりしない限り見えなかった海や川の魚も、この手法により、水を汲むだけで調べることができるようになりました。さらに、ある生物の分布域が温暖化の影響で寒冷地へシフトしていくといった、大規模な変化を捉えるのにも有効です。
サンプルを集める方法は簡単で、市民や学生など多くの人々が参加できるため、環境DNA調査は、地域の自然を理解し保全するための重要なツールになると期待されています。
本号の特集では、いま普及しつつある環境DNA調査はどのようなものか、どのように役立つのかなど、さまざまな視点からわかりやすく紹介しています。
| 【特集】 | 環境DNAで探る生物情報 | 3 |
| 水に残された生き物の痕跡から、生物多様性のデータベースをつくる | 4 | |
| バケツ一杯の水からすんでいる魚がわかる技術 | 6 | |
| 海運の現場で環境DNAを集める | 9 | |
| 多様な昆虫類の現状を知るために | 12 | |
| 環境DNA調査の広がりと今後の期待 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | ―蚊は吸血小器官を知っている!?―蚊が血を吸い、味わうしくみの謎に迫る | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #102 光のマジックに挑戦! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第13回 | 甲殻類に寄生する甲殻類フクロムシの奇妙な生存戦略 | 26 |
| かはくレポート | ミャンマーの自然史解明に向けた取り組み (国際協力編) | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2024年

マスクをした顔(上段)とマスクをしていない顔(下段)。
私たちは他者とコミュニケーションを取る際、その人の顔の表情や視線などから多くの情報を得て、それらを会話などに役立てています。
しかしコロナ禍においては、私たちは普段からマスクを着用して顔の下半分を隠して生活を送ることになりました。
このことが他者とのコミュニケーションにおいて大なり小なり影響を及ぼしたことは想像に難くありません。
心理学の分野では、マスクの着用が他者とのコミュニケーションに与える影響について、さまざまな研究が進んでいます。
本号の特集では、そのような最新の成果について紹介しています。
| 【特集】 | 「顔によるコミュニケーション」 | 3 |
| 顔や表情から得られる情報とは? | 4 | |
| マスクが顔の魅力やコミュニケーションに与える影響 | 6 | |
| 子どもの「表情を読み取る力」はマスク生活で影響を受けたか? | 9 | |
| 顔の皮膚の動きや顔を見る角度は年齢の印象をどう変える? | 12 | |
| 私たちは無意識に相手の表情をまねている | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | ―建物、人体、美術品などに映像を投影する技術─
プロジェクションマッピングの可能性を広げる |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #101 地磁気を調べてみよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第12回 | 産めよ、増えよ、地に満ちよ !? | 26 |
| かはくレポート | 特別展「鳥~ゲノム解析で解き明かす新しい鳥類の系統~」に寄せてゲノム時代にふさわしい鳥の新しいイメージを! | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

今月の表紙は、オーストラリアのシドニー北西に位置するブルーマウンテンズ国立公園の山々。周辺には広大な森林が広がり、90種類ともいわれる多くのユーカリが山麓を覆っています。写真を見ると、山々が青く靄もやっている様子が見て取れます。
これはユーカリなどの植物から大量に放出された生物由来揮発性有機化合物(BVOCs)が日差しを受けて青く反射しているためと考えられています。
ブルーマウンテンズの名前もそこから名づけられたといわれます。こうした「青い靄」は「ブルーヘイズ(blue hazes)」とよばれ、世界各地で確認されています。
画像提供:Shutterstock
| 【特集】 | 植物気候フィードバック ~植物と気候の相互作用を探る~ | 3 |
| 植物と気候の切っても切れない関係 | 4 | |
| BVOCsを用いた植物のコミュニケーション | 6 | |
| 多成分BVOCsのリアルタイム計測 | 9 | |
| 野外から明らかにする植物の遺伝子の使い方と使われ方 | 12 | |
| 地球システムモデリングにおける植物・気候相互作用 | 15 | |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 海産動物のホヤから、脊椎動物の発生や進化の謎を解き明かす! | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #100 温度計と湿度計を作って大気の状態を観察しよう | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第11回 | “ 落ち穂拾い” が見せる共生関係 植物でつながるサルとシカ | 26 |
| かはくレポート | 総合研究 ミャンマーの自然史解明に向けた取り組み〈フィールド調査編〉 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

国立科学博物館の地球館地下3階、「自然科学系ノーベル賞受賞者―科学者の個性と創造性」展示は、日本初の受賞者である湯川秀樹から始まり(左)、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞の受賞者とその研究を一人ずつ紹介しています。
『milsil』は2008年に創刊し、今号で100号を迎えました(右:過去号の表紙)。当誌のインタビュー後に受賞された山中伸弥先生、吉野彰先生、大村智先生、大隅良典先生(円内:左上から左回り)は、今号のためにメッセージを寄せてくださいました(p.8~9 参照)。
| ~通巻100号に寄せて~ | 国立科学博物館がめざす「科学を文化に」と科学雑誌『milsil』の役割 | 3 |
| 【『milsil』創刊100号記念特集】 | 『milsil』の17年間と日本人のノーベル賞受賞 | 6 |
| 『milsil』に登場していた受賞者たち | 8 | |
| 日本と自然科学分野のノーベル賞のかかわり | 10 | |
| 日本の素粒子物理学とノーベル賞 | 13 | |
| 国立科学博物館とノーベル賞 | 16 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 人とロボットのかかわり方を追究し未来に役立てる | 18 |
| チャレンジ !! 科学冒険隊 | #99 模型を作って筋肉の働きを知ろう | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第10回 | 昆虫や鳥、微生物。多様な種と雌雄で異なる関係を結ぶヒサカキ | 26 |
| かはくレポート | 企画展「高山植物~高嶺の花たちの多様性と生命のつながり~」にみる高山植物の多様性と現状 | 30 |

寄り添うように泳ぐカツオクジラの親子。カツオクジラは、ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科ナガスクジラ属。ナガスクジラ属のなかでは、比較的暖かい海の沿岸域を好む種です。写真は、高知県沖でドローンを使って撮影されました。親子連れの写真が撮影されたのは国内初です。ここは通年でカツオクジラが生息しているため、土佐湾で行われているホエールウォッチングでその姿を見ることができます。
撮影:(c)KURIKURICRAFT 藤井雅巳
| 【特集】 | 「日本近海のクジラ」 | 3 |
| 陸から海に戻った“ 変わり者” 海の哺乳類・クジラ | 4 | |
| バイオロギングで探るマッコウクジラの暮らし | 6 | |
| 5000 kmを超えるザトウクジラの大回遊を追う | 9 | |
| ストランディング調査が明らかにするクジラの生態 | 12 | |
| 小型鯨類のエコーロケーションと受動的音響観測 | 15 | |
| 国立科学博物館にいる日本犬ハチ | 17 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | “乱れて整う” 未解明の物理現象の法則を見つけたい ―扱うのは液晶からバクテリアまで― | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #98 アサガオの動きをタイムラプスで観察しよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第9回 | 別種のウイルスから「殻」を借りる「ヤドカリ」ウイルスの謎 | 26 |
| かはくレポート | 「知られざる海生無脊椎動物の世界」で多種多様な海の生き物を紹介 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

縄文人の暮らしを再現した国立科学博物館の展示(日本館2階北翼展示室)。料理の煮炊きや食物の保管などに用いられた土器は、このように床に座り、粘土を成形して作られていました。そして、焼く前の軟らかい粘土には、彼らの生活の断片が入り込んでいました。土器研究の分野ではいま、最新の科学技術でその断片から当時の詳しい情報を手に入れるプロジェクトが進んでいます。研究者たちが土器を通して見つめているのは、はるか昔の暮らしや生活環境です。本号の特集を読んでから展示室を訪れれば、よりリアルに彼らの生きる姿を感じられるかもしれません。
| 【特集】 | 土器 | 3 |
| 土器を掘る | 4 | |
| タイムカプセルと魔法の杖 | 6 | |
| 土器と民俗例から植物利用を探る | 8 | |
| 縄文時代末期の穀物栽培を科学的に立証 | 10 | |
| 土器残存脂質から調理内容物を探る | 12 | |
| 縄文文化における「繊維土器」を解析する | 14 | |
| 土器の時間から文化変化を明らかにする | 16 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | ―蚊は吸血小器官を知っている!?―
蚊が血を吸い、味わうしくみの謎に迫る |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #102 光のマジックに挑戦! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第13回 | 甲殻類に寄生する甲殻類
フクロムシの奇妙な生存戦略 |
26 |
| かはくレポート | ミャンマーの自然史解明に向けた取り組み (国際協力編) | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

冬眠に入ったシマリス(シベリアシマリス:齧歯目(げっしもく)リス科シマリス属)。シマリスは成体体重が約100gの小型のリスで、背中と顔部分の縞模様が特徴。樹上と地上の両方で生活します。冬眠は、通常10月ごろに始まり、翌年3月ごろまで単独で行います。シマリスは冬眠前に脂肪を蓄えて体重を増やすことはせず、巣内に木の実などの食料を貯蔵し、冬眠期間中の覚醒時(中途覚醒時)に食物を摂取することが知られています。冬眠中の体温はおよそ6℃に下がり、呼吸数も1分間に3~4回にまで低下しますが、中途覚醒する際には体温は37℃ほどまで一気に上がります。冬眠のしくみについてはまだ解明されていませんが、冬眠を制御する遺伝子レベルの発現機構を明らかにするための研究も進められています。
| 【特集】 | 冬眠 | 3 |
| 冬眠の魅力と謎 冬眠研究の現在地点 | 4 | |
| 冬眠中に出産も行うクマの冬眠とその生理 | 6 | |
| コウモリの越冬・繁殖生態と気候変動の影響 | 9 | |
| シマリスの冬眠 | 12 | |
| 人工冬眠の臨床応用をめざして | 15 | |
| サイエンス・インタビュー | カーボンナノチューブの触媒気相成長のメカニズムを見つけ、
量産製造法を開発! |
18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #96 貝の不思議にせまろう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第7回 | クモを操り、網の形を改変する異端の寄生蜂クモヒメバチ | 26 |
| かはくレポート | 博物館・植物園資料を活用した絶滅寸前種に関する情報統合解析
標本を生物多様性保全に活かす |
30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2023年

「忠犬ハチ公」の名で知られる秋田犬・ハチの剥製が国立科学博物館の日本館2階北翼に常設展示されています(展示の経緯など詳細はp.17 をご覧ください)。ハチの後ろには甲斐犬(クロ)、南極観測隊に同行したカラフト犬(ジロ)も並んでいます。
今年(2023 年)はハチ生誕100 年の節目にあたり、ハチの生まれ故郷である秋田県大館市をはじめ、待ち合わせの目印としても有名なハチの銅像がある東京都渋谷区などでは、記念の催しも行われています。
※表紙右下のハチのイラストは、国立科学博物館ミュージアムショップのグッズにも使用されています。
| 【特集】 | 日本犬 | 3 |
| 日本犬を通して日本文化を振り返る | 4 | |
| 日本犬の成り立ちをゲノムから探る | 6 | |
| 富山県小竹貝塚に埋葬された縄文犬 MAIBUN 小竹貝塚研究プロジェクト | 9 | |
| 日本犬らしさを探る イヌの進化と「性格」 | 12 | |
| 日本犬の保存とハチ公の思い出 | 15 | |
| 国立科学博物館にいる日本犬ハチ | 17 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 安全で安価な「飲む体温計」を開発 -健康維持や医療に役立てる!- | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #95 振り子で物理の法則を体験しよう | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第6回 | ヌルデの遺伝子を操って虫こぶを形成 ヌルデシロアブラムシ | 26 |
| かはくレポート | 特別展「和食~日本の自然、人々の知恵~」に寄せて 山菜・野菜を自然科学から考える | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
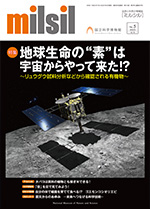
【特集】地球生命の”素”は宇宙からやってきた⁉ ~リュウグウ試料分析などから確認される有機物~
小惑星探査機「はやぶさ2」は、2019年2月22日に小惑星リュウグウへのタッチダウンを成功させ、リュウグウ表面のサンプル採取に成功しました。4月5日には、衝突装置によって人工クレーターを生成、7月11日には2回目のタッチダウンを行い、地下物質のサンプルを採取しました。「はやぶさ2」は2020年12月5日にサンプルの入ったカプセルを分離し、オーストラリアで無事に回収されました。採取したサンプルの分析により、アミノ酸などの有機物や水の存在などが確認されており、地球生命誕生のための原材料の起源を理解するための貴重な情報が得られました。
| 【特集】 | 地球生命の“素”は宇宙からやって来た!? ~リュウグウ試料分析などから確認される有機物~ | 3 |
| 小惑星リュウグウと地球外有機物 | 4 | |
| 小惑星リュウグウ試料から見つかった可溶性有機分子 | 6 | |
| 小惑星リュウグウ試料中の黒い固体有機物 | 9 | |
| 地球外物質に含まれる核酸塩基の検出とその意義 | 12 | |
| 生命を構成する糖を隕石から検出 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | タバコは異科の植物とも接ぎ木できる!-研究に行き詰まった、ダメ元の試みから大発見!- | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #94 「 音」を目で見てみよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第5回 | 自分の体で細菌を育てて食べる!? ゴエモンコシオリエビ | 26 |
| かはくレポート | 企画展 震災からのあゆみ -未来へつなげる科学技術- | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

照葉樹林はブナ科、クスノキ科などの常緑広葉樹を主体とした森林で、日本では関東から北陸以南の低地に広く分布しています。森林に広がる常緑樹の厚くて光沢のある葉からこの名がつけられました。写真上は、成熟した照葉樹林で20m以上にまで育つ常緑広葉樹のイスノキ(マンサク科)の高木。写真左下は、上空から見た照葉樹林。ブロッコリーのようなもこもことした樹冠が並びます。写真右下は、常緑広葉樹のタブノキ(クスノキ科)。葉は硬くつやがあり、夏に実をつけます。
| 【特集】 | 照葉樹林~失われゆく日本の原風景~ | 3 |
| 照葉樹林とは 未来へ残すために知っておきたいこと | 4 | |
| 綾の照葉樹林 森林と結びつく人々の暮らしと文化 | 6 | |
| 鎮守の森 社寺林としての照葉樹林 | 9 | |
| 台風が多い環境条件で成立する照葉樹林 | 12 | |
| 照葉樹の木材利用 森とつながる人々の暮らし | 15 | |
| サイエンス・インタビュー | 折り曲げて貼れる画期的な「ペロブスカイト太陽電池」の開発をリード! | 18 |
| チャレンジ!! 科学冒険隊 | #93 歯車を使ったおもちゃを作ろう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第4回 | 藻類の葉緑体を盗んで光合成!?ウミウシの1 種 チドリミドリガイ | 26 |
| かはくレポート | 「黒潮に注目した地史・生物史・人類史」巨大海流「黒潮」の役割を理解する | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

【特集】ブラックホール~予言された謎の天体に迫る~
銀河の中心に存在する巨大ブラックホールから放出される膨大なエネルギーによって、銀河風(銀河外部に向けて大規模にガスが噴き出す現象)が吹き荒れ、星の材料である星間物質が吹き飛ばされる様子の想像図。131 億年前に存在した銀河を、国立天文台 泉拓磨氏ら国際研究チームがアルマ望遠鏡により観測し、銀河に吹き荒れる巨大ブラックホールの嵐を発見しました(2021 年)。これにより、ブラックホールの活動が銀河の成長に大きな影響を与えることが明らかにされ、銀河とブラックホールが互いに影響し合いながら進化してきたことが示されました。
| 【特集】 | ブラックホール~予言された謎の天体に迫る~ | 3 |
| ブラックホールとはどのような天体なのか? | 4 | |
| ついに捉えたブラックホール | 6 | |
| ブラックホールジェットの謎 | 9 | |
| 超巨大ブラックホールの燃料貯蔵庫「トーラス」を解き明かす | 12 | |
| 遠方宇宙探査からブラックホール誕生の謎に挑む | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | グルテンの構造を可視化する麺の透明化技術を開発─グルテンの構造の違いが食感の差を生む─ | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #92 水の色や夕焼けを再現してみよう | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第3回 | その関係はまるでマトリョーシカ人形!?ヤマトシロアリと共生微生物 | 26 |
| かはくレポート | 標本から読み解く日本の生物多様性 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

気候変動に伴う気温上昇により、日本でも農作物の品質や収量に影響が出始めるなか、栽培が難しかった熱帯・亜熱帯のフルーツにも熱い視線が注がれています。国内産のトロピカルフルーツが食卓に並ぶ日が、やがてやってくるかもしれません。
写真上はマンゴー、下段左からパパイア、レイシ(ライチ)、スターフルーツ。
| 【特集】 | 日本で育てるトロピカルフルーツ | 3 |
| 地球温暖化と熱帯果樹栽培 | 4 | |
| トロピカルフルーツ図鑑 | 7 | |
| 日本におけるパッションフルーツ品種の開発と課題 | 9 | |
| 訪花昆虫を利用した熱帯果樹の安定生産技術 | 12 | |
| 画像解析や近赤外分光によりライチの実を壊さずに評価する | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 市民の力を借りて、マルハナバチの全国分布を推定─マルハナバチの生息環境保全をめざす─ | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #91 自然のなかのフィボナッチ数を調べよう! | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第2回 | 常識破りの対抗手段 托卵鳥にだまされない センニョムシクイ なぜカッコウの雛は排除されないのか? | 26 |
| かはくレポート | 企画展「ボタニカルアートで楽しむ桜」 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

【特集】ラン ~究極の多様性を知る・守る・伝える~
国立科学博物館筑波実験植物園のラン科コレクションを用いて研究し発表した新種。
左上から時計回りに、デンドロビウム・スズキィ(Dendrobium suzukii T.Yukawa)、ドリティス・ナマタンエンシス(Doritis natmataungensis T.Yukawa, Nob.Tanaka & J.Murata)、マラクシス・イワシナエ(Malaxisiwashinae T.Yukawa & T.Hashim.)、パフィオペディルム・プラティフィルム(Paphiopedilum platyphyllum T.Yukawa)、シテンクモキリ(Liparispurpureovittata
Tsutsumi, T.Yukawaet M.Kato)、シンビジウム・ワダエ(Cymbidium wadae T.Yukawa)。
| 【特集】 | ラン ~究極の多様性を知る・守る・伝える~ | 3 |
| 多様性の迷宮・ラン | 4 | |
| 昆虫によって創出されたランの“花のかたち”とその多様性 | 6 | |
| 切っても切れない菌根菌との関係 | 9 | |
| ランを増やす技術のイノベーション | 12 | |
| 新しいランを創る | 15 | |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 生物と機械を融合させたバイオハイブリッドロボットの開発をめざして | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #90 静電気の不思議 | 22 |
| 生き物たちの不思議な関係 第1回 | ヤドカリの「宿」をつくるイソギンチャク!? ヒメキンカライソギンチャク | 26 |
| かはくレポート 解き明かされる地球と生命の歴史 | -化学層序と年代測定- | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2022年

【特集】高分子科学の明日を拓く~環境への配慮と機能性を満たす新技術~
京都大学大学院工学研究科・沼田圭司教授(理化学研究所環境資源科学研究センター・チームリーダー)の研究チームは、遺伝子組み換え技術により、大気中の二酸化炭素と窒素を固定しクモ糸シルクタンパク質を合成する海洋性紅色光合成細菌をつくり出し、細菌から抽出・精製したタンパク質を繊維化することに成功しました(p.3、p.5参照)。写真は、海洋性紅色光合成細菌を効率よく培養するための大量培養装置。クモ糸シルクタンパク質繊維は、石油などから生産される化学繊維に代わる新たな高分子素材として期待されています。
| 【特集】 | 高分子科学の明日を拓く~環境への配慮と機能性を満たす新技術~ | 3 |
| 環境に配慮した機能性高分子材料の開発をめざして | 4 | |
| 分解・劣化・安定化を理解して新しい高分子材料をデザインする | 6 | |
| ハイドロゲルの分解性の理解と医療応用 | 9 | |
| 天然ゴム廃棄物を有価物へと変換するための微生物酵素の開発 | 12 | |
| 植物由来ビニル化合物の特徴を活かしたバイオベースポリマー開発 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 外出困難な人のための“分身ロボット”を開発 ─「孤独の解消」に取り組むロボット研究に挑む─ | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #89 波で模様をつくろう | 22 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑩ | 新種の鉱物の研究 | 26 |
| かはくレポート 特別展「毒」によせて | 博物館が毒に注目する意味 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

【特集】台風 ~地球温暖化で変化する台風~
国際宇宙ステーション(ISS)から撮影された、日本周辺を通過する令和3年台風第10号(2021年8月8日午前11 時半ごろ)。8 月5日に沖縄付近で発生した台風は、東海・関東沖を通過。上陸はしませんでしたが、三宅島では24時間雨量で267mmと8月1か月分を上回る雨量を観測しました。また、このころ日本付近には台風第9号、10号、11号と3つの台風が発生していました。
| 【特集】 | 台風 ~地球温暖化で変化する台風~ | 3 |
| 地球上最強の低気圧-台風 | 4 | |
| 地球温暖化は台風にどのような影響をもたらすのか | 6 | |
| 航空機観測で上空から台風を探る | 9 | |
| 台風による風水害の実態と災害リスクを減らす取り組み | 12 | |
| タイフーンショット計画 2050年、台風の脅威を恵みに | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 膜タンパク質の構造を解明! | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #88 11月8 日に、月食を観察しよう | 22 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑨ | 人類が抱える環境問題と鉱物 | 26 |
| かはくレポート | 総合研究から見えた科学技術史・自然史資料が語る多様なモノガタリ | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

表紙で紹介するようにウイルスの形は球形や正二十面体などの正多面体、棒(線)形などさまざまです(①古細菌ウイルスの1種、③タバコモザイクウイルス、④ノロウイルス)。なかには二十面体の頭部に脚のような尾部がついたアポロ月着陸船のような形のカウドウイルス(②)も見られます。また、細菌と同じくらいの大きさをもつ巨大ウイルス(⑤ピソウイルス)も近年次々に見つかっています。
| 【特集】 | 知られざるウイルスの素顔 ~生物の進化や多様性に関与するウイルス~ | 3 |
| ネオウイルス学:自然界におけるウイルスの役割をひもとく | 4 | |
| 染色体に組み込まれたボルナウイルス | 6 | |
| 病気を起こさないウイルスは植物に何をもたらすのか | 9 | |
| 温泉の中の古細菌ウイルスから探る原始ウイルス | 12 | |
| 新型コロナウイルスの起源を考える | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 植物の再生メカニズムを解明する 切られた植物から芽や根が出るのはなぜ? | 18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #87 クモの姿や、あみや巣を観察しよう! | 22 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑧ | 資源として利用される鉱物 | 26 |
| かはくレポート | 博物館展示の新たなモデル 巡回展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」 | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

福岡県北九州市沖約15km(響灘沖)に設置され、実証運転が行われている浮体式洋上風力発電システム「ひびき」。水深50 ~100 mという浅水域を対象に、日本近海の気象・海象条件に適した低コストの次世代浮体式洋上風力発電システムおよび施工方法の開発・検証を目的に実施されている新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プロジェクト「次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究」により製作されたバージ型鋼製浮体と2 枚翼風車を組み合わせた実証機。実海域で2019年から運転試験を行い、性能やコストを検証しています。
| 【特集】 | 脱炭素社会をめざす新たなエネルギー技術 | 3 |
| カーボンニュートラルを実現するための新エネルギー技術 | 4 | |
| 塗ってつくる日本発の次世代太陽電池 | 6 | |
| 洋上風力発電の開発加速に向けてドップラーライダーで海上風を測る | 8 | |
| 超臨界地熱資源の活用 | 10 | |
| 次世代エネルギーとして期待される水素とアンモニア | 12 | |
| 高性能蓄電池の開発とその応用リチウムイオンから革新型蓄電池まで | 15 | |
| サイエンス・インタビュー
科学のいま、そして未来 |
細胞が放出するエクソソームや miRNA の情報伝達メカニズムを診断や治療、
予防に活かす |
18 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #86 洗濯のりで遊ぼう! | 22 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑦ | 宇宙から来た鉱物-隕石の科学 | 26 |
| かはくレポート | 特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」によせて 博物館と宝石コレクション | 30 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

イエネコは、食肉目ネコ科ネコ属に分類されるリビアヤマネコが家畜化したものと考えられています。家畜化した時期について詳しいことは不明ですが、農耕の開始に伴い保存した穀物をネズミによる食害から守る番人として役立った(しかも肉食のネコは穀物に手を出さない)ことが、人類のパートナーとして認められるきっかけだったといわれます。イエネコとして人に飼われるなかでさまざまな品種が生まれ、現在ではペット動物として世界中で飼育されています。
| 【特集】 | ネコの科学~もっと知りたい“ 自由気ままな隣人”のこと~ | 3 |
| ネコはなぜ人とともに生きるようになったのか | 4 | |
| 遺伝子からみたネコの世界 | 6 | |
| ネコは自分の名前を聞き分ける | 9 | |
| ネコを苦しめる腎臓病の新薬を開発して寿命を延ばす | 12 | |
| 日本に生息するヤマネコ | 15 | |
| 国立科学博物館による黒潮の生物調査 | 17 | |
| Focus | リサイク材料から新しいコンクリートを開発 | 18 |
| 標本の世界 | 海生哺乳類の標本について | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #85 ネコをじっくり観察しよう | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑥ | ジルコン-地球の歴史を知る鉱物- | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

流れ着いた浜辺で芽を出すヤシ。海水に浮く構造をもち、種子を海流に運ばせることによって広い分布域を獲得した植物は海流散布植物とよばれます。フィリピン諸島付近から東シナ海を北上し日本南岸を流れる黒潮(p.3 などの流路図を参照)は、世界最大規模の海流で、熱帯域から水や熱を日本周辺に運んでいますが、生物の移動にも大きくかかわっています。ココヤシの実も黒潮に乗ってしばしば日本の浜辺に漂着することが知られていますが、温帯域では越冬できないため生育は難しいとされています。
| 【特集】 | 黒潮 ~世界最大規模の海流は日本に何をもたらす?~ | 3 |
| 黒潮とは | 4 | |
| 黒潮が日本の気候・気象に及ぼす影響 | 6 | |
| わが国の水産資源を支える豊穣の海「黒潮」 | 9 | |
| 黒潮が日本に運んだ熱帯植物 | 12 | |
| 黒潮はいつ生まれ、どう変化してきたのか? | 14 | |
| 国立科学博物館による黒潮の生物調査 | 17 | |
| Focus | 折紙を数学的に考えて工学に応用 | 18 |
| 標本の世界 | 多様な植物化石コレクション 国立科学博物館の標本群とその活用をめざして | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #84 円周率を自分で求めてみよう! | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ⑤ | 人気で色合いもさまざまな宝石-ベリル(緑柱石) | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2021年
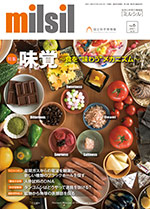
【特集】味覚~食を“ 味わう” メカニズム~
五感のひとつである「味覚」は、味み物ぶっ質しつを化学的に検知する特殊な感覚です。表紙写真では、舌などにある味蕾で受容される5つの基本味(甘味・苦味・酸味・塩味・うま味)を感じる代表的な食材を紹介しています。5つの基本味は、食物のおいしさを感じるためだけでなく、酸味を感じることで腐敗した食べ物に気づくことができるなど、危険なものを避け、安全に栄養を摂取するためにも重要な味なのです。
| 【特集】 | 味覚 ~食を“味わう”メカニズム~ | 3 |
| 味覚のしくみと味を認知する脳の働き | 4 | |
| 味覚受容体の構造と働き | 6 | |
| 味の数値化と個人嗜好の可視化 | 9 | |
| 挑戦! 霊長類の味覚を培養細胞で再現する | 12 | |
| 口腔外に発現する味覚センサーの多機能性 | 15 | |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 星間ガスからの電波を観測し新しい種類のブラックホールを探す | 18 |
| 標本の世界 | 人骨試料のDNA サンプリングからCT撮影まで | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #83 ダンゴムシはどうやって迷路を抜ける? | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ④ | 鉱物から地球の表層部を探る | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

ハナガサクラゲ(刺胞動物門ヒドロ虫網)は、ラテン語で「美しい」を意味する「formosa 」が学名についているとおり、傘から伸びる短い棒状の触手の先が黄・紫・緑色などの蛍光色に彩られる華やかな姿が特徴です。傘の直径はおよそ10 ~15 cm。あまり泳ぎ回らず、海藻などについている様子が見られます。
| 【特集】 | クラゲ | 3 |
| クラゲとはどのような生き物か? | 4 | |
| クラゲの生活史 ~生き残るための生存戦略~ | 5 | |
| クラゲに刺されるとは? またその毒素とは? | 8 | |
| 北極海のクラゲ | 11 | |
| クラゲと共生する生き物たち | 14 | |
| ヒトの食料としてのクラゲ | 16 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 電気を流す“ 電気細菌” を研究! | 18 |
| 標本の世界 | 100年前の繭に巨大カイコの模型!? | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #82 植物の色で布を染めてみよう! | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ③ | 地球深部を鉱物から探る | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

ソフトロボットの開発では、生物の形態をただまねるのではなく、普遍的で有用な原理を抽出し、構造や運動のバイオメカニクス(生体力学)をロボットに活用する取り組みが進められています。東京大学の新山龍馬氏らが試作した「ダチョウ首ロボットアーム」もその一つです。ダチョウの解剖学的観察からわかった筋肉と腱けんの配置をワイヤ駆動機構に反映し、やわらかい首の動きを再現することをめざしています。
| 【特集】 | “やわらか”発想で拓くソフトロボット学 | 3 |
| ソフトロボット学が切り拓くしなやかな未来 | 4 | |
| タコ腕コンピュータ | 6 | |
| やわらかいロボットとバイオメカニクス | 9 | |
| 化学エネルギーのみで駆動するゲルマシン | 12 | |
| 柔軟ロボット機構の考案と具現化 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 筋肉の感覚を計測、再現する技術を開発! | 18 |
| 標本の世界 | ハーバリウムは宝の山 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #81 花の色水できれいな小びんを作ろう! | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ② | 身近な鉱物 氷の科学 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

写真は、小笠原諸島・父島の南西沖にある南島から望む父島・ジニービーチ。世界自然遺産区域に含まれる南島には、石灰岩が侵食されてできたカルスト地形が広がり、すでに絶滅したヒロベソカタマイマイの半化石などが見つかっています。外来種グリーンアノール(トカゲのなかま)が侵入していないため、父島で絶滅が心配されている昆虫の避難場所としても貴重な場所となっています。対岸の父島・ジニービーチは白い砂浜が広がる景勝地。
| 【特集】 | 小笠原諸島の自然 ~「世界自然遺産」登録から10年~ | 3 |
| 大陸から隔絶された島々の特異な自然環境と生態系 | 4 | |
| “陸続き”になったことがない小笠原諸島の地質 | 6 | |
| 古代DNA研究がひもとくアジアへの人類渡来 | 9 | |
| 小笠原諸島のカタツムリ 楽園とその危機 | 12 | |
| アホウドリの新繁殖地形成に向けた取り組み | 15 | |
| FOCUS 科学者の探究心にせまる | 光合成をやめ、菌類に寄生する植物の謎を解く | 18 |
| 標本の世界 | 引き継がれる魚類標本 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #80 平らな紙からたまご形を作ろう! | 24 |
| 鉱物の世界を楽しむ① | 鉱物学の夜明け | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| 次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

2003年に、インドネシアのフローレス島にあるリアンブア洞窟の約10 ~ 6 万年前の地層から発掘された化石をもとに復元されたフローレス原人と、当時、島で共存していた動物たち(小型化したゾウのなかまピグミー・ステゴドンや大型化したジャイアント・ラットなど)。フローレス原人の身長は1 m ほどしかなく、脳の大きさも猿人並みの小ささです。孤立した島では、動物の身体が大きくなったり小さくなったりする「島とう嶼しょ効果」という現象が起きることが知られています。これによりフローレス原人も小型化したのではないかと考えられています。
| 【特集】 | アジアの人類史 ~アジアに拡散した人類たちの進化を追う~ | 3 |
| アジアの人類史がおもしろい! | 4 | |
| かつてアジアには多様な原人や旧人がいた | 6 | |
| 古代DNA研究がひもとくアジアへの人類渡来 | 9 | |
| 渡海による移住に成功したウォーレシアの旧石器人 | 12 | |
| 化学分析が明らかにする世界最古級の土器とその使用法 | 15 | |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 動物の模様や形の謎を数理的な法則から解き明かす | 18 |
| 標本の世界 | ここは美術館? いえ、博物館です! 災害研究資料としての絵画や写真 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #79 植物の水の通り道を観察しよう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 最終回 | 微細な証拠物を鑑定する先端分析技術 繊維片、ガラス片、陶器片から真実を見つける! | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

月はおよそ29.5日で地球の周りを1周します。月は太陽に照らされた面が輝くため、地球から見ると、約29.5日ごとに満ち欠けを繰り返し、月が太陽と反対の方向にあるとき、写真のように満月になります。月が常に同じ面を地球に向けているのは、公転周期と自転周期が同じ、つまり地球の周りを1周(公転)する間に1回自転するためです。
| 【特集】 | 月 ~再び注目される地球に最も近い天体~ | 3 |
| 月の謎はどこまで明らかにされたのか? | 4 | |
| 月周回衛星「セレーネ」の科学的成果 ~日本が達成した「アポロ計画」以来最大規模の月探査~ | 6 | |
| 月の起源 -巨大衝突説の新展開 | 9 | |
| 月面上の降りたいところへ着陸 ~「SLIM」プロジェクトの挑戦~ | 12 | |
| 国際協力で月面探査をめざす ~日本が推進する宇宙探査シナリオ~ | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | ネコには思い出がある? ネコは推理できる? | 18 |
| 標本の世界 | 関東平野の貝化石 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #78 洗うだけじゃない! 石けんで遊ぼう | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第12回 | 高かったこのセーター、本当にカシミヤ100%?混用率も見抜く獣毛鑑別の技術 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2020年

理化学研究所と富士通が共同で開発したスーパーコンピュータ「富岳」。2020年6 月の高性能計算技術に関する国際会議「ISC2020」で発表された性能ランキングにおいて、「富岳」は「TOP500」をはじめ4 つの指標で世界一に輝きました。日本のスーパーコンピュータが「TOP500」で1 位になるのは、2011年11月の「京」以来8 年半ぶりのことです。「富岳」は現在も開発・調整が進められており、2021年度より本格運用が始まる予定です。
| 【特集】 | 「富岳」が拓く計算科学の未来 | 3 |
| スーパーコンピュータ「富岳」がめざすもの | 4 | |
| 「富岳」プロジェクトを振り返って | 5 | |
| シミュレーションで探る新型コロナ対策 | 6 | |
| プレシジョン・メディシンを加速する「創薬ビッグデータ統合システム」の推進 | 9 | |
| サイバー空間を活用した革新的ものづくり | 12 | |
| 世界最大規模のAI 基盤をめざす「富岳」 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | カキとキウイフルーツの性決定のしくみを解明! | 18 |
| 標本の世界 | 石灰岩洞穴からは今後も大発見が続く | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #77 海岸の漂着物から海洋ごみ問題を考える! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第11回 | 最前線の毒物分析で中毒事件に挑む | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

海氷が広がる北極海を航行する海洋地球研究船「みらい」(海洋研究開発機構)。耐氷構造を備える世界でも最大級の海洋観測船で、これまでに北極海でも数多く大気・海洋観測を行い、日本の北極観測研究においてさまざまな成果を挙げています。
| 【特集】 | 北極 ~地球最北の海で何が起きているのか~ | 3 |
| 北極は地球温暖化の影響が激しく現れる場所 | 4 | |
| 北極の海氷減少と海洋環境の変化 | 5 | |
| 北極の気候変化は環境にどのような影響を及ぼすのか | 8 | |
| 北極海洋生態系の変化 | 11 | |
| 環境変化と北極域先住民 | 14 | |
| 北極海航路と世界 | 16 | |
| サイエンス・インタビュー | アルツハイマー型認知症薬を開発、根本治療薬の創出にも挑む | 18 |
| 標本の世界 | 日本の隕石と南極隕石コレクション | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #76 どんぐり虫を観察しよう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第10回 | 重なった指紋も識別可能!指紋分析の最新技術 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

シジュウカラにとって、卵やひなを襲うヘビは恐ろしい天敵であり、巣に近づこうとするヘビを見つけると、親鳥は「ジャージャー」という特別な鳴き声を発して威嚇します。写真は、別のシジュウカラにこの鳴き声(録音)を聞かせたときに見せたヘビを探す様子です。この特別な鳴き声は、シジュウカラにヘビのイメージを思い描かせていることが実験から明らかになりました。
| 【特集】 | 認知科学でさぐる鳥の“心” | 3 |
| 鳥の認知、ヒトの認知 | 4 | |
| ハトが見る世界、ヒトが見る世界 | 6 | |
| カラスの社会の基盤をさぐる | 9 | |
| 小鳥の鳴き声にも単語や文法がある!? シジュウカラ語・大研究 | 12 | |
| 同種と異種のさえずりを区別する基準をさぐる | 16 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 新しい機能や性質をもつ高分子を設計! | 18 |
| 標本の世界 | 標本は生き物を絶滅から救う研究にも役立つ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #75 ゆっくりできる氷、あっという間にできる氷 | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第9回 | 宝石を鑑別する最先端技術 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

農産物のなかでもイチゴは数多くの品種が栽培されており、登録品種は250 種を超えます。表紙のお皿の上に15 種類のイチゴを並べてみました。味わいや香りだけでなく、よく見ると形状にも違いがあります。
また、切ってみると、中が白いものや紅いもの、黄色っぽいものなどもあり、個性豊かです。① 紅ほっぺ ② おおきみ ③ いばらキッス ④ 桃とう薫くん ⑤ 福ふく羽ば ⑥ 恋みのり⑦ おいC ベリー ⑧ もういっこ ⑨ 夏あかり ⑩ あまえくぼ ⑪ やよいひめ ⑫ とちおとめ ⑬ レッドパール ⑭ 麗れい紅こう ⑮ ロマンス
| 【特集】 | おいしく育てやすい作物育成への挑戦~農作物と品種改良~ | 3 |
| 品種改良とは何か? | 4 | |
| 「コシヒカリ」を超える米をめざして | 6 | |
| 世界一の人気野菜・トマトの品種改良 | 9 | |
| ブドウの品種改良と新品種「シャインマスカット」の育成 | 12 | |
| 品種改良の最先端技術 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 化石と胚発生の研究を駆使して脊椎動物の進化を読み解く 新しい視点で、横隔膜やカメの甲羅の起源に迫る! | 18 |
| 標本の世界 | 都会は巨大な石材標本室 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #74 飛んでくる電波をキャッチするしかけを作ろう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第8回 | 頭蓋骨から個人を識別する、顔を復元する スーパーインポーズ法と復顔法 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

日本列島周辺の海底地形。東北地方の沖合(太平洋側)を南北に走る日本海溝、その南に続く伊豆- 小笠原海溝、さらに本州・四国の沖合に南海トラフが広がる日本近海の海底は、3つのプレートがぶつかり合う(三重会合点)、世界でも珍しい複雑な地形が形成されています。
| 【特集】 | 日本列島の誕生と変遷~変動する極東の海底と大地~ | 3 |
| 大陸から分離した日本列島 | 4 | |
| 日本列島を隆起させた「東西圧縮」 | 8 | |
| 北海道はどのようにして誕生したか | 11 | |
| 日本列島に衝突した南の海の火山島 | 14 | |
| 西日本で起きた1500万年前の特異なマグマ活動 | 16 | |
| サイエンス・インタビュー | 地球にやさしい材料、セルロースナノファイバーの開発と実用化を推進 | 18 |
| 標本の世界 | ミニチュアのような標本 ~小さなガの標本を作る~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #73 断層を作ってみよう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第7回 | この“ 太平洋産クロマグロ”や、あの“ 国産黒毛和牛”は本物?食品偽装を見抜く技術 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

アルマ望遠鏡のアンテナと夜空に輝く天の川。日本を含む22の国と地域が協力して運用するアルマ望遠鏡は、星や惑星の材料となる塵やガス、生命の材料になり得る物質が放つ電波をとらえることができます。
| 【特集】 | 地球外生命を探せ!~アストロバイオロジー最前線~ | 3 |
| ようこそ、アストロバイオロジーの新世界へ | 4 | |
| 系外惑星の観測で新展開を迎えたアストロバイオロジー | 5 | |
| 太陽系における生命探査 | 8 | |
| 宇宙の化学とアミノ酸探査計画 | 11 | |
| 惑星誕生のメカニズムを大型望遠鏡による観測で探る | 13 | |
| 第二の地球での光合成 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | サルの「会話」からヒトの言語の起源を探る | 18 |
| 標本の世界 | 古代人の姿を明らかにする人骨試料 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #72「 紋切り遊び」で対称の形を楽しもう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第6回 | 共通語を話しても出身地がわかる!? 方言から犯人を探る言語プロファイリング | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |
2019年

葉の上の水滴の水を飲むクロオオアリ。クロオオアリは、ほぼ日本全国に分布し、住宅地や公園など人の暮らしの近くでも多く見られます。働きアリの体長が約7~12mmと、日本に棲息するアリの中ではムネアカオオアリと並びもっとも大型です。
| 【特集】 | アリ ~その多様な生き方に迫る~ | 3 |
| アリの多様な生き方は飛ぶことをやめて可能になった? | 4 | |
| 外来アリ侵略を科学する | 6 | |
| アリの社会を支えるケミカルコミュニケーション | 9 | |
| “ 働かない” 働きアリが巣を滅ぼす!? | 12 | |
| 海外のアリたちの多様な生き方 | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | はるか遠くの分子雲を観測して、惑星誕生の謎に迫る! | 18 |
| 標本の世界 | 恐竜化石展示と研究におけるレプリカの活用 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #71 野菜やきのこで紙を作ろう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第5回 | お札や硬貨に施された最先端の偽造防止技術! | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

【特集】リモートセンシング
世界最大級の地球観測衛星である陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」(表紙右下)によって撮影された富士山とその周辺域。富士山西面の大おお沢さわ崩くずれ(潤うる井い川がわ源流部)や南東面の宝ほう永えい山ざん(富士山の側火山)と宝永火口もはっきりと写し出されています。「だいち」には、地図作成、地域観測、災害状況把握、資源調査などに役立てるため、「高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)」など3つのセンサが搭載されています。
| 【特集】 | リモートセンシング ~宙から地球を見守る~ | 3 |
| リモートセンシングとは? | 4 | |
| 植物機能リモートセンシングとスマート農業 | 6 | |
| 衛星リモートセンシングと地球環境モニタリング | 9 | |
| 宇宙からの災害監視 | 12 | |
| 宇宙考古学 | 15 | |
| サイエンス・インタビュー | 極限環境で生きるアーキアのDNAの複製、修復のしくみを解き明かす | 18 |
| 標本の世界 | スウェーデンで出会った日本の植物のタイプ標本 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #70 街路樹を観察しよう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第4回 | 不明文字鑑定 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

【特集】プランクトンの世界
ヘッケルのチャレンジャー号報告書『放散虫類報告』(1887 年)の図版(Pl. 60)より。ナセラリア目放散虫の新種個体(ディクチオフィムス属の5種:①〜⑥、ラムプロミトラ属の2種:⑦・⑧、トリポキルティス属の2種:⑨・⑩)を側面や上下面などのさまざまな方向から観察して描いた標本。赤く見えるのは中心囊で、見やすくするためにベンガルレッドで染色しています。
| 【特集】 | プランクトンの世界 | 3 |
| プランクトンとは? | 4 | |
| 赤潮を引き起こすプランクトン | 6 | |
| ガラスの殻をもつ未知のプランクトン | 9 | |
| 植物プランクトンの長期モニタリングから見えること | 12 | |
| プランクトンの形態の様に魅せられた動物学者ヘッケル | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 長生きで、がんにもならない!? ハダカデバネズミの秘密を研究! | 18 |
| 標本の世界 | 魚類の分類学とタイプ標本 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #69 失敗しない! 水の中の微生物観察 | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第3回 | ビルやブロック塀のコンクリート内部を透視! | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース & おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

沖縄の島々へ、3万年以上前にたどり着いた祖先たち。彼らはどうやって困難な航海を成功させたのでしょうか? 国立科学博物館「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、その謎を探るため、本年6~7月に、丸木舟で台湾から与那国島をめざす実験航海を計画しています。
| 【特集】 | 島に渡った動物とヒト | 3 |
| 動物にとって島とは何か? | 4 | |
| 琉球列島への陸生爬虫類の侵入 | 6 | |
| 鳥なら島を“ひとっ飛び” か? | 9 | |
| 島に適応した動物 | 12 | |
| 3万年以上前に琉球の海を越え、島へ渡った祖先たち | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 植物を材料にして新しいプラスチックをつくる! | 18 |
| 標本の世界 | 科学・技術史分野の資料としてのあかり | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #68 昆虫標本を作ろう! | 24 |
| 真実を見抜く技術! 第2回 | 靴に付着した砂や泥が暴く真実 | 28 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース& おもしろニュース | 33 |
| milsil カフェ/次号予告/定期購読のお知らせ/編集後記 | 34 |

DNAなどさまざまな情報の活用が進んでいる収蔵標本群。左上:タダマイマイ(国立科学博物館収蔵標本)。右上:オガサワラヨシノボリ(国立科学博物館収蔵標本)。中央左:コヒョウモンモドキ成虫(写真提供:中濱直之)。中央右:イワキアブラガヤ(上部参照)。下:ニホンカワウソ(高知県のいち動物公園所蔵)。
| 【特集】 | DNAと保存科学で生物標本を活かす | 3 |
| 博物館の生物標本の意義とさらなる活用 | 3 | |
| 標本のDNA解析と保存科学 | 6 | |
| 絶滅種ニホンカワウソの系統関係 | 8 | |
| 絶滅種? 外来種? 80年前の標本からイワキアブラガヤの由来を探る | 11 | |
| 標本から見えた草地性チョウ類の盛衰 | 14 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 短い年月の間に起こる生き物の進化を検証! | 17 |
| 標本の世界 | 小さな化石が語る地球の気候変動 | 20 |
| 真実を見抜く技術! 第1回 | 知っていることを暴く!? ポリグラフ検査でわかること | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #67 バランス ~重心って何だろう?~ | 26 |
| DNAを知る 最終回 | DNAの変化と生物の進化 | 30 |
| NEWS&TOPICS | 世界の科学ニュース& おもしろニュースを10 分で | 32 |
| milsil カフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

一番下で空を見上げるデイノニクスの頭上には、4枚の翼で枝から枝に滑空するアンキオルニス、2枚の翼になった始祖鳥、尾羽をもつようになった孔子鳥、白亜紀後期の鳥類ヴェガビスと、ジュラ紀後期から白亜紀後期の「羽毛恐竜」から鳥類への進化の代表的な種が描かれています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 「結晶スポンジ法」を確立し分子構造の解析に革命をもたらす | 3 |
| 【特集】恐竜から鳥へ-進化の軌跡 | 6 | |
| 鳥類の恐竜起源説-この50年を振り返る | 6 | |
| 軟組織から見る鳥への進化 | 11 | |
| 回廊を巡り、恐竜の巣作りを探る | 14 | |
| 恐竜のつくられ方 | 17 | |
| 標本の世界 | 50cm彗星写真儀-日本で最初の本格的シュミットカメラ | 20 |
| 日本の国立公園 最終回 | 南アルプス国立公園 ~南限の動植物に出合える、標高3000m級の大山脈~ | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | ♯66 こうじ金を使って甘酒を作ろう! | 26 |
| DNAを知る 第7回 | DNAと医療~遺伝子検査によって可能となること~ | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2018年
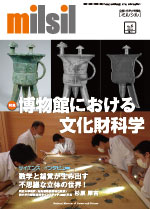
上の3点は、中国古代青銅器か「細線饕餮紋か(「か」は口2つにわかんむりに斗)」の外観(左)とCT画像(中央)、3D断面画像(右)。
下は、正倉院宝庫内での点検作業の様子。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 数学と錯覚が生み出す不思議な立体の世界! | 3 |
| 【特集】博物館における文化財科学 | 6 | |
| 博物館における臨床保存 | 6 | |
| 正倉院宝物を支える保存科学 | 10 | |
| 世界の資料を保存する | 12 | |
| DNAから博物館資料を考える | 14 | |
| 小判を金色に見せる技術「色付」 | 16 | |
| X線CTを用いた文化財の科学調査 | 18 | |
| 標本の世界 | 新時代の菌類標本の活用 | 20 |
| 日本の国立公園 第9回 | 白山国立公園 ~迫力ある火山地形と可憐な高山植物たち~ | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | ♯65 偏光板ってなんだろう? | 26 |
| DNAを知る 第6回 | 遺伝子操作でできること② ~CRISPR-Cas9がもたらした大革命~ | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

変形菌は、単細胞生物とは思えないほど複雑かつ多彩な子実体をつくります。
①ウツボホコリ、②ムラサキホコリ、③ルリホコリ、④ジクホコリ、⑤キラボシカタホコリ、⑥エダナシツノホコリ。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | スマホや電気自動車に欠かせないリチウムイオン二次電池を発明 | 3 |
| 【特集】ふしぎで多彩な変形菌の世界 | 6 | |
| 変形菌とは何か | 7 | |
| 変形菌の系統・進化 | 11 | |
| 単細胞の賢い行動 | 13 | |
| 変形菌の形づくり | 16 | |
| 日本における変形菌の分類研究の系譜 | 18 | |
| 標本の世界 | シーボルトが収集した日本の植物標本 | 20 |
| 日本の国立公園 第8回 | 知床国立公園~流氷がもたらす海と陸の生態系~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #64 きれいな結晶、ふしぎな結晶 | 26 |
| DNAを知る 第5回 | 遺伝子操作でできること①~ゲノム編集が登場するまで~ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

デジタル標高地形図「東京都区部」。「航空レーザー測量」(p.14参照)により得られた詳細なデータで立体的に描かれた東京の地形。江戸城が周囲を低地に囲まれ、守りやすい台地の先端に築かれたこと、外堀が谷を活かして造られたこと、上野や渋谷の地名の由来など、普段は意識しない東京の自然の地形が浮かび上がってきます。
| 【特集】広がる「地図」の世界 | 3 | |
| 地図と私たち | 3 | |
| 多様な地図を楽しむ | 7 | |
| 明日を確かめ、未来を図る地図 | 10 | |
| 進化する地図 | 14 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | カタツムリを左巻きに進化させた、右利きのヘビ! | 17 |
| 標本の世界 | 棘皮動物クモヒトデ類の入村精一コレクション | 20 |
| 日本の国立公園 第7回 | 伊勢志摩国立公園~人々の営みと自然が融合する景観美~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #63 磯へ行って貝を観察! 貝の標本をつくろう! | 26 |
| DNAを知る 第4回 | DNAの塩基配列を調べる~進化するシークエンシングの技術~ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

堂々たるケヤキの樹形。この木も1個の小さな種子の発芽から出発し、毎春小枝を伸ばし、葉をつけることを繰り返して成長してきました。また、存分に伸長できる環境にも恵まれて、この種本来の丸い立派な広葉樹形と成り得たのです。
| 【特集】樹木の科学 | 3 | |
| 木の形を楽しむ | 4 | |
| 木は光を求めて枝を伸ばす | 8 | |
| 樹木はなぜ長寿で巨大になれるのか | 11 | |
| 樹木の成長を芽鱗痕でたどる | 14 | |
| ウツクシマツに見る樹形の遺伝 | 16 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | アリをだましてアリ社会に入り込む!? | 17 |
| 標本の世界 | きのこの「絶滅種」を標本から探る | 20 |
| 日本の国立公園 第6回 | 屋久島国立公園~荘厳、神秘に満ちた巨木と水の森~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #62 昆虫をさがせ! 虫採りトラップを作ろう! | 26 |
| DNAを知る 第3回 | DNA複製の精妙なしくみ② | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

| 人間の脳を構成する神経細胞は、脳を越え、身体全体に伸びる。身体は、外部の社会との相互作用を通し、その情報を神経に、そして脳に伝える。すなわち、脳は社会と切り離すことができない。「知能」を考えるということは、人間の、そして生物の社会を考えることであるともいえる。 |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 電気自動車や風力発電に不可欠なネオジム磁石を発明 | 3 |
| 【特集】人工知能と人間 | 人工知能の研究から迫る人類の知 | 6 |
| 忘れることで人の知能が生まれた | 10 | |
| 赤ちゃんの認知形成からみえてくる人間の認知 | 13 | |
| 人類の知の歴史と複眼思考 「造形」と「コミュニケーション」 | 15 | |
| 人工知能が創る人類の未来 | 18 | |
| 標本の世界 | 札幌博物場旧蔵産業史資料が語る明治の日本と博物館の役割 | 20 |
| 日本の国立公園 第5回 | 三陸復興国立公園~変わらない自然と復興の兆しを見せる町並み~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #61 光を観察! ピンホールカメラで遊ぼう! | 26 |
| DNAを知る 第2回 | DNA複製の精妙なしくみ① | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

小笠原諸島での潜水調査の折に撮影した写真です。暖かな海の太陽の光が届く水深には、このように枝状、塊状、テーブル状などさまざまな形をした造礁サンゴ(褐虫藻を共生させているサンゴ)が生息しています。 表紙の写真提供:並河 洋
| 【特集】サンゴの知られざる世界
|
「サンゴ」と名のつく動物たち | 3 |
| ミドリイシサンゴの進化の軌跡 | 5 | |
| 生き物のすみかとしてのサンゴとサンゴ礁 | 8 | |
| 宝石サンゴの世界 | 11 | |
| 海底に潜るイシサンゴ | 15 | |
| Focus 科学者の探究心にせまる | 北米とアジアの恐竜の生態、進化を解き明かす | 17 |
| 標本の世界 | わが国のコケ植物研究の黎明期を語る笹岡久彦コレクション | 20 |
| 日本の国立公園 第4回 | 奄美群島国立公園~シマの文化が守り続ける固有種~ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 化学冒険隊 | #60 スマホで読み解く!? 雪の手紙 | 26 |
| DNAを知る 第1回 | DNA、遺伝子、ゲノムの違いが分かりますか? | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2017年
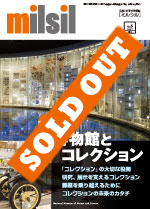
私たちの「見たい、知りたい」という素直な知的好奇心を満たしてくれる博物館。その展示は、博物館が保有するさまざまな標本や資料といったコレクションに支えられています。上は、地球に誕生した生き物がたどった多様化の道のりを、床の光のラインと標本で表した展示(科博地球館1階「系統広場」)。下は、科博筑波研究施設で保管されている、木製電気自動車。
| 巻頭インタビュー | 「コレクション」の大切な役割 | 3 |
| 【創刊10周年記念特集】博物館とコレクション | 6 | |
|
研究、展示を支えるコレクション
|
偉大なアマチュアが集めた世界的コレクション | 8 |
| 科学研究を支えるコレクション | 12 | |
| 展示をもっと楽しむために! | 16 | |
|
課題を乗り越えるために |
知の財産を遺すための努力 | 19 |
| 3.11で再認識された標本レスキューの意義 | 20 | |
| 豪雨に襲われたエジソンの資料を守る! | 22 | |
| “生きた標本”リビングコレクション | 24 | |
|
コレクションの未来のカタチ |
古代DNA解析から人類の歴史に迫る | 26 |
| データベースでつなぐ世界のコレクション | 30 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

これは羅臼岳(北海道斜里郡)で撮影したシモフリゴケの写真です。深い霧の中からときおり顔をだすコケの緑に、皆さんは何を感じ取るのでしょう? コケは時に驚くほど美しく、幻想的な光景を私たちに見せてくれます。
| 【特集】ようこそ! コケの世界へ
|
3 | |
| 「コケ植物」とは何なのか | 4 | |
| 琥珀に閉じ込められたコケが教えてくれること | 7 | |
| 水を浄化するコケの原糸体 | 10 | |
| ミズゴケが地球を救う | 12 | |
| コケを愛する日本人 | 14 | |
| Focus 科学者の探求心にせまる | 遺伝子が2倍に増える!?「遺伝子重複」から進化の謎を解く | 17 |
| 標本の世界 | 斎藤報恩会貝類コレクション | 20 |
| 日本の国立公園 第3回 | 上信越高原国立公園 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #59 コケを観察!コケテラリウムを作ろう! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色―最終回 | 「共感覚」からみえてくる色の世界のなぞ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

太陽フレアのイメージ。太陽フレアとは太陽の表面でときおり起こる爆発現象のこと。爆発とともにプラズマや強力な放射線が惑星空間に放出されます。そして巨大な太陽フレアが発生すると、地球や社会にさまざまな影響を及ぼすことがわかってきました。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 記憶のメカニズムを分子や遺伝子から解き明かす | 3 |
| 【特集】太陽フレア | 太陽フレアとスーパーフレア | 6 |
| 宇宙天気予報-1 | スーパーフレアから地球を守れ | 10 |
| 太陽活動史を読み解く | 13 | |
| 宇宙天気予報-2 | 深層学習で宇宙天気の変化を予測 | 15 |
| 生命誕生と太陽フレア | 18 | |
| 標本の世界 | 石の上にも?年―フサカツギの新たな標本を発見するまでの道のり | 20 |
| 日本の国立公園 第2回 | 富士箱根伊豆国立公園 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学探検隊 | #58 トンボと仲良くなろう | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第10回 | 色にまつわる印象や感情はどこからくるのか | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

南鳥島南東部で発見されたマンガンノジュールの密集地帯。左下には単位面積当たりのマンガンノジュールの量を調べる「コデラート」と呼ばれる計測器の四角い枠が見えます。右上は調査を行った有人潜水調査船「しんかい6500」です。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 日本列島の成り立ちを四万十帯の調査から解き明かす | 3 |
| 【特集】日本の深海底に眠る鉱物資源を探せ! | いま、なぜ海洋鉱物資源なのか? | 6 |
| 有用金属元素の宝庫、海洋熱水鉱床を探す | 8 | |
| 人口熱水孔上にチムニーが急成長 | 11 | |
| 海底に広がる“マンガンと鉄の黒い塊” | 13 | |
| 第4の海底鉱物資源・レアアース泥の探査・成因研究の最前線 | 17 | |
| 標本の世界 | 弥生時代の英雄? シャーマン? 土井ヶ浜124号人骨の謎 | 20 |
| 日本の国立公園 第1回 | 国立公園がもたらすもの | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学探検隊 | #57 簡易カイロと瞬間冷却パックで温度変化を体験しよう | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色―第9回 | 温度によって色が変わるインクのしくみ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
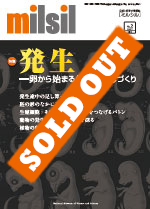
テドイツの生物学者ヘッケルによるさまざまな動物の発生過程の図(1874年)。ヘッケルは「個体発生は系統発生を繰り返す」という「反復説」を唱えた。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 世界に先駆け、光を自由に操る「フォトニック結晶」を創出 | 3 |
| 【特集】発生―卵から始まる生き物の形づくり | 6 | |
| 発生途中の足し算・引き算 | 7 | |
| 胚の形のなかに進化をみる | 10 | |
| 生殖細胞:それは次の世代に命をつなげるバトン | 13 | |
| 動物の発生を比較して進化を探る | 15 | |
| 植物の卵からの形づくり | 18 | |
| 標本の世界 | DNAバーコード用鳥類仮剥製標本コレクション | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 最終回 | コガタアカイエカ 驚きの飛翔能力で日本脳炎ウイルスを運ぶ | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #56 めざせ! においの名探偵! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第8回 | 自然界には存在しない花色づくりに挑む | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

みなさんの家ではどのようなお雑煮を食べますか? お雑煮の具や味付けは地域によっても違いますし、きっと「家の味」というものもあるでしょう。しかし「だし」は必ず含まれているはず。どうぞじっくりと味わってみてください。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | インスリンの研究から、糖尿病大規模データベース構築へ | 3 |
| 【特集】だし | 6 | |
| だしとは何か | 6 | |
| だしの生みだす食の多様性 | 8 | |
| 「だし」のエッセンス、うま味の科学 | 9 | |
| 鰹節と鰹節だし | 12 | |
| なぜコンブは海の中でだしが出ないのか? | 15 | |
| ラーメンスープの中で活きる「だし」―その進歩と発展 | 16 | |
| 世界のうま味、日本のうま味 | 19 | |
| 標本の世界 | 植物園の生きたコレクションが教えてくれる植物の秘密 | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第10回 | ハリガネムシ カマドウマを操って川へと帰る小さな旅 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #55 身のまわりにあるもので音の正体をさぐる | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第7回 | 生きものがまとう燦めく色彩「構造色」の秘密に迫る | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2016年

いい匂いで何とか悪臭を消そうとしたり、無臭が好まれたり、時代によって、匂いに対する人の好みや意識は変化してきました。現在はほのかに香る「微香」が好まれるようです。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | ニュートリノの性質から消えた反物質の謎を解く! | 3 |
| 【特集】匂い | 6 | |
| 匂いとは何か―嗅覚のしくみ | 6 | |
| 「匂いの遺伝子」で進化をたどる | 10 | |
| 匂いと心―香りの認知 | 12 | |
| 日本人にとっての香り | 14 | |
| 香りをつくる(開発)と香りをつける(応用) | 16 | |
| フルーツの香りがする魚をつくる | 18 | |
| 標本の世界 | ムカシトンボ―謎めいていた生きている化石 | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第9回 | カエルツボカビ 日本起源のカビ?!その不思議な「旅」 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #54 冬の夜空を楽しもう | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第6回 | 鉱物の色を活用した岩絵具の世界 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

学生時代、生物顕微鏡を授業で使った方は多いでしょう。覚えていますか?ピントを合わせるときは「対物レンズとプレパラートを遠ざけつつ調整する」のでしたね。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 未知の研究領域を求めてオートファージのメカニズムを解明 | 3 |
| 【特集】顕微鏡 | 6 | |
| 光学顕微鏡の種類と多様性 | 6 | |
| ミクロの世界を切り開く―ロバート・フック著『顕微鏡観察誌』 | 8 | |
| 徹底解剖 光学顕微鏡 | 11 | |
| 電子顕微鏡が開く新たな世界 原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡 | 14 | |
| 日本最初の雪の自然科学書『雪華図説』 | 17 | |
| 珪藻 ―大自然が生んだミクロの幾何学デザイン | 19 | |
| 標本の世界 | 日本を代表するモササウルス類化石が世に出るまで | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第8回 | クロマグロ 太平洋を2か月で横断する長距離泳者 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #53 タイドプールで磯の生物を観察しよう! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第5回 | 天然素材で繊維を染める「草木染め」の科学 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
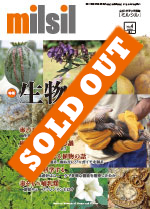
毒をもつ生物は意外と身近にいる。そういうとドキリとするかもしれない。今号の特集は生物毒がテーマだ。「正しくこわがる」ことができるよう、毒について関心をもっていただければ幸いである。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 98%が水でできたアクアマテリアルで世界を驚かせる! | 3 |
| 【特集】生物毒 | 6 | |
| 毒とはなにか―生物毒と人間 | 6 | |
| 麻痺性貝毒の不思議―毒はどこからやってくる? | 8 | |
| 毒にも薬にもなる植物の話―パン酵母で薬を造る、毒のないジャガイモを創る | 11 | |
| ハブ毒を科学する―どうしてユニークで多様な機能を獲得したのか | 14 | |
| 毒をもつ哺乳類―珍獣キューバソレノドンとは? | 17 | |
| 標本の世界 | 化石発掘現場に放置された“ごみ”が考古学的な資料になるとき | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命―第7回 | サバクトビバッタ 大雨と季節風が促す大発生の旅 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #52 お菓子作りで地形を学ぼう | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第4回 | 誰もが識別できる色使いを考える | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

ジャイアントケルプとよばれるコンブのなかま。海で最大の光合成生物であり、「藻場」という陸上の森のような生態系をつくる。(カリフォルニア州サンタカタリナ島で撮影。)
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | fMRIの脳画像から夢を読み解く新技術を開発 | 3 |
| 【特集】海藻―海の植物のしたたかな生き方― | 6 | |
| 生活環にみる海藻の生き方の多様性 | 7 | |
| 海の森をつくる巨大海藻―ジャイアントケルプの形と生活史戦略 | 9 | |
| 紅藻の複雑怪奇な生殖様式 | 12 | |
| 生きた石になる海藻―石灰藻の生存戦略と海の環境 | 14 | |
| 世界へ分布を拡げる日本の海藻 | 17 | |
| 標本の世界 | 岩石標本になった硯 | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第6回 | 納豆菌 タクラマカン砂漠から黄砂に乗る微生物 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #51 意外に知らない 身近な生き物アリを観察しよう! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第3回 | 色を共有するためのしくみづくり | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

今号の表紙は科博の研究者による、まさざまな研究調査風景です。
①自然教育園での毎木調査 ②伊豆諸島と小笠原諸島の間の無人の島々、豆南諸島における調査 ③ブータンで行ったセイタカダイオウの調査 ④電気技術史資料の調査 ⑤石垣島白保竿根田原洞窟遺跡の発掘 ⑥アラスカ・トンシナ地域におけるジュラ紀島弧地殻断面の調査
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | みんなに科学好きになってもらいたい!~国立科学博物館の担う役割~ | 3 |
| 【特集】もっと知りたい!カハクのすべて | 6 | |
| 輝く!道具たち | 6 | |
| これぞ自慢の一品(動物研究部) | 8 | |
| 研究者のフィールドワークに密着!(植物研究部) | 12 | |
| 筑波実験植物園―7000種の植物を育成保存 | 15 | |
| Q&A形式 地学の難問に挑戦!(地学研究部) | 16 | |
| 骨はすべてを知っている―頭骨が語る人類の歴史(人類研究部) | 20 | |
| 電子機器から望遠鏡、科学者の手紙やノートまで!―人間の作り出したものが研究対象(理工学研究部) | 24 | |
| 街なかに隠された江戸時代の“お宝”(附属自然教育園) | 28 | |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #50 科学の目で、どんぐりをかこう | 30 |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

あえて説明するまでもありませんが、絹(シルク)の織物と組みひもです。シルクは長い歴史をもつ天然繊維ですが、いま、新しい素材としても注目を集めています。本号の特集は、その伝統に根差した革命的な技術スポットを当てています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 過剰な免疫反応にブレーキをかける制御性T細胞を発見 | 3 |
| 【特集】知るシルク―カイコが生み出すヒトの暮らしと未来 | 6 | |
| カイコとヒトの深い関係―家畜化された昆虫カイコの利用 | 6 | |
| 「光るシルク」―高機能シルクの実用化に向けて | 10 | |
| シルクを設計する―遺伝子組み換えカイコとクモ糸シルク | 13 | |
| シルクの構造の解明とシルク人工血管開発への挑戦―衣料から医療へ | 16 | |
| 標本の世界 | ラン科クモキリンソウ属の分類研究とタイプ標本 | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第5回 | マリモ 故郷は日本?! アメリカ、ヨーロッパに拡がった分布 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #49 家庭用の重そうで実験しよう! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第2回 | 霊長類の色覚の進化の軌跡 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2015年

今号の特集では、ワイン、ビール、日本酒造りを切り口として、微生物とのかかわりについて紹介します。また、酒造りの中心である酵母について、どのような生物なのかも詳しく解説します。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 蛍光タンパク質で生命現象を鮮やかにとらえる | 3 |
| 【特集】酒造りの微生物学 | 6 | |
| 酵母とは―その分類と生態の多様性 | 6 | |
| ワイン造りと酵母の働き | 8 | |
| ワインをまろやかにする「マロラクティック発酵」とは? | 11 | |
| ビール酵母の個性と香味造り | 12 | |
| 日本酒ができるまで | 15 | |
| キラー酵母と酒造り | 19 | |
| 標本の世界 | 標本ゲノムの解析から進化を観察する | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第4回 | ハチクマ 世界に公開!往復2万㎞の旅 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #48 レーウェンフック式顕微鏡をペットボトルで手作りしよう! | 26 |
| 色の世界―色の科学がおりなす景色― 第1回 | 私たちに色が見えるわけ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 |

北山アルプス立山連峰の太郎平(富山県富山市)の土壌断面。上部は泥炭質、下部には数千年前に生育したと考えられる黒泥質の層が2つあり、その間に火山ガラスが入っている。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 大気と海洋の作用が生み出すエルニーニョ現象を解明 | 3 |
| 【特集】土壌の世界―私たちの足もとの宇宙 | 6 | |
| 土壌って何だろう? | 6 | |
| 土壌の生成―火山噴火と植生遷移 | 10 | |
| 土壌中の生き物ホットスポット、堆積腐植層とは | 12 | |
| 落ち葉の下に広がる世界 | 15 | |
| 土の粒々から考える身近な環境、地球の環境 | 16 | |
| 標本の世界 | 微細藻類のエキシカータ | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第3回 | グンバイヒルガオ 長距離を旅する植物の種子の秘密に迫る | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #47 電池なしで聞こえる傘ラジオを手作りしよう! | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 最終回 | 進むSI基本単位の再定義とその意義 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次回予告 | 34 |
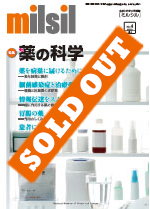
現代にはたくさんの薬が存在します。そのどれもが人類の英知の結晶です。薬にはどのような工夫がなされているのでしょうか。また、どうして効果があるのでしょうか。今号の特集、「薬の科学」をお楽しみください。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 天然生理活性物質の人工合成で世界をリードする「Dr.全合成」 | 3 |
| 【特集】薬の科学 | 6 | |
| 薬を病巣に届けるために―投薬経路と製剤 | 6 | |
| 細菌感染症と治療薬―細菌と抗菌薬の攻防戦 | 8 | |
| 情報伝達をスムーズに―脳に作用する薬の働き | 12 | |
| 胃腸の薬―作用のしくみと服用上の注意点 | 16 | |
| 患者にやさしい製剤 | 18 | |
| 標本の世界 | 仮晶―鉱物の“化石” | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第2回 | アサギマダラ 2400㎞の旅路を多くの人の手で解明 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #46 夏の雲、積乱雲にせまる!! | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第11回 | 五感で感じる“おいしさ”を数値化する | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

西マリアナ海嶺の南部で採取されたオオコンニャクイタチウオ(アシロ科)の仔魚。体の下部分にある外腸は、変態期に入るとすべて体内に入ってしまう。体長は113.3mm。 写真提供:福井篤
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 最先端の天体望遠鏡で第二の地球を探す! | 3 |
| 【特集】変態のふしぎと多様性 | 6 | |
| 動物の変態―幼生という特別な時期をもつ動物たち | 7 | |
| ホヤの変態のふしぎ | 10 | |
| 深海性魚類のミステリアスな個体発育 | 11 | |
| 昆虫の変態のメカニズムに迫る | 12 | |
| おたまじゃくしの尾がなくなるしくみ―幼生のしっぽはカエルから免疫的に“非自己=異物”として拒絶してなくなる | 15 | |
| 標本の世界 | 出土遺物から日本における金銀の生産技術を探る | 20 |
| 旅する生き物―地球をめぐる命― 第1回 | ニホンウナギ 往復6000㎞、壮大な旅の謎 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #45 プランクトンと仲よくなろう! | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第10回 | 国際単位系に属さない単位の位置づけを知る | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

【特集】宇宙で生物実験─宇宙ステーション・「きぼう」のライフサイエンス分野の成果
高度400㎞の宇宙空間を1周約90分で周回する国際宇宙ステーション(ISS)です。世界の5つの宇宙機関が参加し、日本の実験棟「きぼう」では、微小重力環境を利用して地上では不可能な材料実験や生命科学実験が行われています。写真提供:宇宙航空研究開発機構
| サイエンスインタビュー 科学のいま、そして未来 | 放射菌の生産する物質で、寄生虫病から多くの命を守る | 3 |
| 【特集】宇宙で生物実験―宇宙ステーション・「きぼう」のライフサイエンス分野の成果 | 6 | |
| 世界15か国が参加する有人宇宙施設「国際宇宙ステーション」―日本が運用する「きぼう」日本実験棟は、究極の実験環境 | 6 | |
| 宇宙でのライフサイエンス実験はどこまでみえてきたか―細胞からメダカ(個体)まで | 9 | |
| 宇宙で骨が減るメカニズムの解明に挑む | 10 | |
| 宇宙飛行士の健康を支える宇宙医学研究―宇宙医学研究の成果と今後の展望 | 13 | |
| 宇宙でのタンパク質結晶生成を地上の創薬研究につなげる | 16 | |
| 輸血液を補完する人口酸素運搬体の実用化をめざして | 19 | |
| TOPICS 2015年の国際宇宙ステーション・「きぼう」日本実験棟 | 19 | |
| 標本の世界 | 地質時代や環境の生物指標「有孔虫」 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口-世界結晶年2014 最終回 | 結晶の形に見るミクロの秩序 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #44 浮いて走る!リニアモーターカーにせまる!! | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第9回 | さまざまな“はかる”を網羅するSI組立単位 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次回予告 | 34 |

国立科学博物館の長年にわたる調査で、約115万㎡(東京ドーム約25個分)の広さがある皇居には、動植物など約6000種の生物が生息していることが確認されました。そのうち45種は日本初記録種です。皇居はまさに生物多様性に満ちた貴重な場所でもあるのです。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 窒素の安定同位体を使って生態系を読み解く | 3 |
| 【特集】皇居の生物―東京の中心に広がる生物多様性 | 6 | |
| 皇居で見られたチョウとガ―18年にわたる皇居調査の結果から | 7 | |
| 皇居に暮らすタヌキ―糞と追跡調査からわかったこと | 10 | |
| 皇居の維管束植物相と新種フキアゲニリンソウ | 13 | |
| オオタカのすむ森 | 14 | |
| 皇居に生きる絶滅危惧藻類 | 16 | |
| 皇居の地衣類は大気環境をかく語りき | 17 | |
| 標本の世界 | 生きた植物標本 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口―世界結晶年2014 第10回 | ミクロの世界に刻まれたマクロな物語―天然と人口の結晶 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #43 冬の生き物さがし | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第8回 | 明るさの単位、カンデラ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2014年

サンゴは藻類の一種である褐虫藻と共生している生き物です。この褐虫藻が光合成を行います。光合成能力をもたない動物が、光合成能力をもつ藻類などと共生している例はサンゴ、イソギンチャク、クラゲ、貝などに見られます。写真はユビエダハマサンゴ。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 物質の性質を数学で解き明かす理論物理学のパイオニア | 3 |
| 【特集】光合成―そのしくみと多様性 | 6 | |
| 光合成研究へのいざない | 6 | |
| 光合成をする生き物の多様な世界―動物の中で生きる藻類 | 10 | |
| 光合成生物は合体しながら進化した | 13 | |
| 光合成しない植物の進化 | 13 | |
| 光合成が変えた地球と生物 | 14 | |
| 人工光合成とは何か?―研究の現状と将来展望 | 17 | |
| 標本の世界 | 化学遺産と国立科学博物館所蔵化学者資料 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口―世界結晶年2014 第9回 | 科学は“よく見る”ことから始まる―電子顕微鏡による究極の物質構造研究 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #42 科学の力でよごれを落とそう! | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第7回 | 温度の単位ケルビンと、“はかる”の関係 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

南極昭和基地のオーロラ。太陽風のプラズマ粒子が磁気圏に侵入したあと、いったん地球の夜側に運ばれ、何らかの原因で地球に向かって加速され、極地方に降り注ぐことで起こります。そのため、大規模なカーテン状のオーロラは、基本的に夜側の現象です。
写真:第54次南極地域観測隊 井 智史(気象庁地磁気観測所)隊員撮影。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 薄膜太陽電池の開発で、地球温暖化問題の克服に挑む | 3 |
| 【特集】「地磁気」~過去・現在・未来を映す地球のバリア~ | 6 | |
| 地磁気とは何か | 7 | |
| 地磁気精密観測から見える世界 | 12 | |
| 目に見えない磁気を博物館で体感する | 16 | |
| 岩石・地層からの地磁気観測 | 17 | |
| 標本の世界 | 生体復元「歴史を旅する日本人」 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口-世界結晶年2014 第8回 | 分子を閉じ込める結晶:包接結晶 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学探検隊 | #41 ろうそくと自作ランプで「燃える」を考えよう | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第6回 | 量子力学を用いた再定義が検討される「電流」 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次回予告 | 34 |
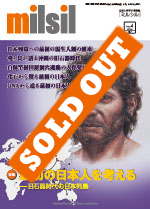
港川人のアジア南方起源説をもとに描いた復元モデル。画家は山本耀也氏です。1号頭骨の特徴を反映させながら、眼などにアボリジニ的要素を入れて作成されました。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 鳥の「歌」から、ヒトの言語の起源に迫る | 3 |
| 【特集】最初の日本人を考える―旧石器時代の日本列島 | 6 | |
| 日本列島への最初の現生人類の渡来 | 8 | |
| 骨と貝が語る沖縄の旧石器時代 | 9 | |
| コラム 白保竿根田原洞穴遺跡の人骨発見 | 12 | |
| 化石から探る最初の日本人 | 13 | |
| DNAから探る最初の日本人 | 16 | |
| 標本の世界 | 国産初の反射望遠鏡を探る | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口‐世界結晶年2014 第7回 | 地球深部を構成する物質―超高圧下のX線実験で明らかにされた鉱物たち | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #40 石ころを拾って土地の歴史をさぐろう | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第5回 | 放射線に関する単位、ベクレルとシーベルト | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

威風堂々と立つのは、南極大陸アマンダ湾に面した集団繁殖地のコウテイペンギンの成鳥です。雌雄は不明。ここは南極特別保護地区に指定されており、立ち入るには各国の関係機関の発行する許可証が必要です。撮影した11月は南極では初夏で、雛が巣立つ約1か月前に当たります。背景に広がる氷河の手前には、親鳥と雛の集団が立っています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 謎の植物病原体の正体を世界に先駆けて解明 | 3 |
| 【特集】極限環境の生物 | 6 | |
| 鯨骨生物群集とホネクイハナムシ | 8 | |
| ヒマラヤの温室植物―セイタカダイオウ | 12 | |
| コウテイペンギン―南極の冬という極限の環境を生き抜く工夫 | 16 | |
| 標本の世界 | 目で見てわかる教育用機器 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口―世界結晶年2014 第6回 | 結晶構造解析が解き明かす光合成の謎 | 22 |
| 親子で遊ぼう! 科学冒険隊 | #39 海からのおくりもの 海藻おし葉を作ろう | 26 |
| 世界をはかる―単位の基準とその役割― 第4回 | 「質量」と「物質量」の単位の関係と再定義 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
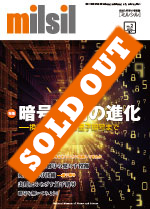
今月は普段の生活の中にも深く浸透している暗号の歴史と技術を紹介します。特集タイトルの「換字式暗号」とは、普通の文を別の文字や記号などに置き換えて暗号文を作成する暗号のことです。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 高温高圧の環境をつくり出し地球の内部構造の謎に挑む | 3 |
| 【特集】暗号技術の進化―換字式暗号から量子暗号まで | 6 | |
| 暗号の歴史―暗号はどのように発展してきたか | 6 | |
| 暗号を解いてみよう! | 10 | |
| ネット社会と暗号の果たす役割 | 11 | |
| 究極の暗号技術―量子暗号 | 15 | |
| 実用化をめざす量子暗号 | 19 | |
| 標本の世界 | 工学分野から注目される魚類液浸標本 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口‐世界結晶年2014 第5回 | 結晶学が開いたライフサイエンスの扉 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #38 音の正体をさぐろう!音の形を見よう!! | 26 |
| 世界をはかる‐単位の基準とその役割‐ 第3回 | 歴史とともに大きく変わった「長さ」の定義 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

日本に生まれ育った人なら誰でも一度は富士山の絵を描いたことがあるでしょう。古くから歌に詠まれ、絵に描かれ、その美しい容姿は日本人一人ひとりの心に刻まれてきました。一方、かつての噴火による災難から「荒ぶる山」として、畏敬の念をもって信仰の対象でもありました。こうした日本人の精神風土や文化、さらには海外の芸術家などにも大きな影響を与えてきたことから、富士山は2013年、世界遺産(文化遺産)に登録されました。登るもよし、描くもよし、拝むもよし。さて、あなたにとっての富士山は、どのような山なのでしょう?
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | ビックデータを使いこなし新たな情報活用の道を探る | 3 |
| 【特集】富士山~世界に名だたる名峰はどのような山なのか~ | 6 | |
| 富士山の噴火史から何が読めるか? | 7 | |
| 富士山の地下構造とマグマ・噴火予測 | 11 | |
| 富士山の植物群落 ―ふもとから頂上まで | 15 | |
| 湖水・湧水ガイド | 19 | |
| 標本の世界 | アンモナイトの成長初期の殻をみる | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口‐世界結晶年2014 第4回 | 青色発光ダイオードの実現‐高品質窒素ガリウム単結晶が果たした役割 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #37 たこ上げの名人になろう! | 26 |
| 世界をはかる‐単位の基準とその役割‐ 第2回 | 究極の精度を求めて進化する「秒」 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2013年

1989年の第1回国際度量衡総会で質量の単位として採択された国際キログラム原器。この原器は約120年の時を経て、プランク定数による質量の再定義によって、その役目を終えようとしています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 特殊なカプセルを使って安全で手軽ながん治療の実現を | 3 |
| 【特集】単位をめぐる最先端科学 | 6 | |
| 基本単位の定義が変わるとどうなるのか | 6 | |
| 光格子時計‐新たな原子時計の開発に挑む | 10 | |
| 量子効果で電流を定める | 14 | |
| ボルツマン定数から温度の単位を定義 | 17 | |
| 標本の世界 | 港川人とサキタリ洞での新発見 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口‐世界結晶年2014 第3回 | 高温超伝導の発見と結晶学が果たした役割 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #36 実りの秋“ひっつきむし”をさがそう | 26 |
| 世界をはかる‐単位の基準とその役割‐ 第1回 | 世界共通の“ものさし”、国際単位系ができるまで | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

地球をこの角度から見ると海の占める割合が最大になります。水の惑星とよばれ、表面の7割を海に覆われた青い地球の姿は、宇宙人(もし存在するとしたら)から見ても、太陽系の他の惑星とは異質の存在であることに気付くでしょう。地球の水はどこからやって来たのか。かつては火星にも海があったといわれていますが、なぜ地球だけが生命を育む惑星であり続けたのか。その答えのヒントは今号の特集にあるかもしれません。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 数学の力で、連続の世界と不連続の世界を結ぶ | 3 |
| 【特集】水の惑星「地球」―生命に不可欠といわれる水はどこからやってきたのか | 6 | |
| 生命を育んだ惑星“地球”の起源と進化 | 6 | |
| 地球および火星の“水”はどこからもたらされたのか | 10 | |
| 地球内部の水 | 13 | |
| 系外惑星と水・生命 | 16 | |
| 標本の世界 | 噴火活動が生み出した火山弾が語るもの | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口―世界結晶年2014 第2回 | 結晶学を進歩させたX線と中性子 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #35 スルメイカでせまる!? 巨大イカのなぞ | 26 |
| かたちと科学 最終回 | 自然のなかの形、人がつくり出した形 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

ヤコウタケ(夜光茸)の学名はMycena chlorophos(ミケナ・クロロフォス)。ギリシャ語で「緑色の光」という意味になるそうです。ヤコウタケはわずか数センチメートルの大きさですが、きのこのなかでは非常に明るく光ることで有名です。しかし、どのようなしくみで光っているのかはよくわかっていません。まさに「神秘の光」といえるでしょう。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 化学工業を大きく変える画期的な金ナノ粒子触媒を発見 | 3 |
| 【特集】発光生物―なぜホタルやきのこは光るのか | 6 | |
| 発光生物をめぐる謎―光るきのこを中心に | 7 | |
| 南の島の光るきのこ | 10 | |
| ホタルが光るしくみ―生物発光の化学 | 15 | |
| コラム 発行生物の起源に迫る | 19 | |
| 標本の世界 | 大都市「江戸」の裏側 その3 | 20 |
| 結晶 原子・分子の世界への入り口―世界結晶年2014 第1回 | 結晶学発展の歴史 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #34 パスタブリッジを作ろう! | 26 |
| かたちと科学 第14回 | バリエーションに富む橋の形を決めているのは何か | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

宇宙のように見える表紙は、基本的な細胞の構造を表したカットモデル。電子顕微鏡などの観察で得られたデータから描き起こしたイメージです。私たちヒトの体は受精卵という、わずか1個の細胞から始まり、分裂を繰り返して60兆個もの細胞からなる複雑な生命体へと発達します。小さな細胞の中にも宇宙があり、進化と発生の履歴が刻まれています。ミトコンドリアの謎から、話題のiPS細胞まで、私たちの体の中のミクロの世界の冒険の旅へ、いざ出発!
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 113番目の元素をつくり、知られざる元素の性質を探る | 3 |
| 【特集】ヒトの細胞―最先端科学でみる姿と働き | 6 | |
| ヒト細胞‐発生とその構造 | 7 | |
| ミトコンドリアの正体 | 10 | |
| 繊毛のふしぎ―単細胞生物からヒトまで | 13 | |
| 幹細胞とiPS細胞 | 17 | |
| 標本の世界 | カセミミズ類の連続切片標本 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第10回 | 陸上植物がかかわる4つの共生系 | 22 |
| 共生植物図鑑10 分類索引 | 25 | |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #33 見えないものが見える?手作り霧箱で放射線を見よう! | 26 |
| かたちと科学 第13回 | 生き物の表面構造に学ぶ水の輸送のしくみ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
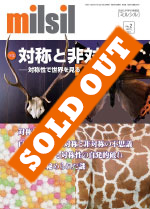
人間は昔から対称を好むらしい。対称性のあるものを美しいと思う。自然界の中にも対照的なものが多い。シカの角や蝶の翅はほぼ左右対称だ。しかし、キリンの縞模様や、自然物ではないが、金平糖の角などは非対称だ。対称と非対称は、どちらも理由があってそうなっている。今回の特集では、さまざまな分野における対称と非対称について考えてみた。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | ロボットスーツHAL(R)を用いて人間の身体機能を補助・拡張・改善する | 3 |
| 【特集】対称と非対称-対称性で世界を見る- | 6 | |
| 対称性の芽 | 6 | |
| 自然界における対象と非対称の不思議 | 9 | |
| ヒッグス粒子と対称性の自発的破れ | 14 | |
| 対称性に秘められた謎 | 17 | |
| 標本の世界 | フォッサマグナミュージアムの翡翠コレクション | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第9回 | 人がつくった植物たち-栽培植物- | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #32 じっくり見れば発見できる!小さな草花の生きる作戦 | 26 |
| かたちと科学 第12回 | ヒトの脳の“錯覚”を数値化して広く応用する | 30 |

すやすや眠る子ども、そして私たちの一生も約3分の1は睡眠に費やされています。これほどまでに長い時間を占めている睡眠にはどんな意味があるのか。睡眠から目覚め、覚醒できるのはどんなしくみなのか。そして、睡眠中に見る夢・・・夢にも役割があるのか。今回は、現代人の睡眠の悩みを含め、ヒトの睡眠についてご紹介します。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 光通信の大容量・高速化技術を開発しインターネットの基礎を支える | 3 |
| 【特集】ヒトの眠りを科学する | 6 | |
| 睡眠と夢 | 6 | |
| 眠りとは何か | 10 | |
| 睡眠と覚醒を切り替える脳のしくみ | 14 | |
| 睡眠のしくみと若い人に起こる睡眠の問題 | 17 | |
| 標本の世界 | 渋川晴海の紙張子製天球儀・地球儀 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第8回 | 「軍拡競走」で進化するゾウムシの長い口 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #31 くるくる回るコマのふしぎ | 26 |
| かたちと科学 第11回 | 共通の構造をもちながらも千差万別なウイルスのかたち | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2012年

日本人1人あたりの鶏卵消費量は年間に300個以上と、世界でもトップクラス。鳥類や爬虫類などの生物も鶏卵のように殻のある卵を産みます。特集ではその卵の機能や形成、進化などを取り上げます。表紙の写真は白い卵ですが、赤い卵もあります。これは鶏種によるもので、栄養価の違いはないようです。またL、Sなどの重量区分も、卵白の量による違いで、卵黄は重量に関係なくほぼ同じ大きさです。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 世界で初めて天然ウナギの卵を採取しその生態を明らかにする | 3 |
| 【特集】卵-その秘められた機能と進化- | 6 | |
| 卵の形/卵の色 | 6 | |
| 卵の色と形のふしぎ | 7 | |
| 恐竜の繁殖:卵と巣 | 11 | |
| ニワトリの卵の発生 | 14 | |
| 食用からワクチン、抗体まで-広がる卵の利用 | 17 | |
| 標本の世界 | シーボルトの日本産甲殻類標本 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第7回 | カンコノキとハナホソガの共進化 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #30 いのちのカプセルたまごのひみつ | 26 |
| かたちと科学 第10回 | "つながり方"の幾何学トポロジーから見るかたち | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

この絵は、安政2年(1855)年、江戸に大きな被害をもたらした安政江戸地震の様子が描かれたものです。この前年、安政東海地震、安政南海地震といった海溝型の巨大地震が立て続けに起こり、安政江戸地震を誘発したのではないかと考えられています。巨大地震は、なぜ連動するのでしょうか?
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | バーチャルリアリティがめざす未来の生活とは | 3 |
| 【特集】超巨大地震の地殻変動がもたらしたもの | 6 | |
| 地殻変動の観測とそこから推定されること | 6 | |
| 沈降か隆起か-過去100年と過去10万年の矛盾する挙動 | 10 | |
| 東北地方太平洋沖地震を地質学的時間スケールでみると何が見えるか? | 14 | |
| 巨大地震がもたらした内陸部の地震活動変化 | 20 | |
| 標本の世界 | クラークの植物標本 | 24 |
| 共生・共進化する植物の世界 第6回 | サンゴと褐虫藻の共生系 | 26 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #29 地震を知ってもしもの時に備えよう | 30 |
| かたちと科学 第9回 | 生き残り戦略がもたらしたさまざまな種子や果実のかたち | 30 |
| NEWS & TOPICS | 36 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 38 |

誰よりも速く走りたい・・・やみくもに練習を重ねるだけでは100分の1秒を縮めることは難しく、運動生理学・バイオメカニクス、栄養学、そしてシューズなど、さまざまな最新科学に支えられて、その願いが実現されていきます。人類の記録はどこまで伸びるのでしょうか。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | インフレーション理論で宇宙創成の大いなる謎に迫る | 3 |
| 【特集】「走る」を科学する | 6 | |
| 走の運動生理学-早く走るための筋肉の条件 | 7 | |
| 人はいかにして速く走るのか-100m走の最新サイエンス | 10 | |
| トップアスリートの食事法-スポーツ栄養学の視点から | 14 | |
| 進化するスポーツシューズ-陸上スパイクシューズの秘密 | 17 | |
| 標本の世界 | 標本から生きた絶滅危惧植物を追いかけて | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第5回 | 渓畔林の共生系~チャルメルソウとミカドシギキノコバエ~ | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #28 海辺の宝さがし! ビーチコーミング入門 | 26 |
| かたちと科学 第8回 | 壮大な時間をかけて変化し続ける銀河のかたち | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

これは、2010年1月15日に中国・青島で撮影された金環日食です。金環継続時間が11分を超えるという今世紀最長の金環日食でした。青島では、15時36分ころに欠け始めて日没直前に金環食になり、そのまま低空の朝焼け雲に沈むという、たいへん美しい眺めになりました。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 新発想のマイクロマシンで医療研究の新しい形を提案 | 3 |
| 【特集】太陽~地球の生命を支える天体~ | 6 | |
| 太陽とはどんな星か | 6 | |
| 太陽観測の歴史 | 9 | |
| 太陽観測衛星「ひので」がとらえた太陽 | 12 | |
| 太陽からもたらされるものと地球の関係 | 16 | |
| 宇宙天体予報 | 18 | |
| 標本の世界 | 大都市「江戸」の裏側 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第4回 | 細胞共生:生物進化の推進力 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #27 太陽の前を月が通過!金環日食を観測しよう! | 26 |
| かたちと科学 第7回 | ナノスケールの世界で人工の「らせん」をつくり出す | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
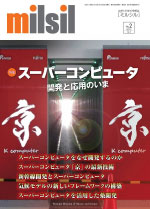
2012年6月に完成、秋から共用開始の予定ですが、本誌発売時点ですでに世界最速の計算速度をもつ日本のスーパーコンピュータ「京(けい)」。どこか和風な響きをもつ名前ですが、万、億、兆、に続く万進法の単位「京(けい)」にちなんでいます。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 生物がつくり出す毒から探る知られざる生命のしくみ | 3 |
| 【特集】スーパーコンピュータ 開発と応用のいま | 6 | |
| スーパーコンピュータをなぜ開発するのか | 7 | |
| スーパーコンピュータ「京」の最新技術 | 10 | |
| 新幹線開発とスーパーコンピュータ | 14 | |
| 気候モデルの新しいフレームワークの構築 | 16 | |
| スーパーコンピュータを活用した薬開発 | 18 | |
| 標本の世界 | 「幻の怪獣」デスモスチルス | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第3回 | 菌根共生~地下に隠された菌類と植物の密接な共生関係~ | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #26 よーく見るとカワイイヤツ イモムシと仲良くなろう! | 26 |
| かたちと科学 第6回 | 見の回りにあふれる「フラクタル」なパターン | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

オキアミを捕食するアデリーペンギン。この画像はペンギンの背中に取りつけられた小型カメラによって得られました。バイオロギングサイエンスの発達により、動物の体に各種小型記録計を取りつけることが可能になり、これまで知られていなかった生態が次々と明らかになっています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 新世紀の錬金術を実現する多孔性金属錯体 | 3 |
| 【特集】生物が記録する科学-バイオロギングサイエンス | 6 | |
| 7つの海で展開するバイオロギングサイエンス | 6 | |
| 動物のカメラがとらえる世界 | 8 | |
| 音で調べる海の中 | 11 | |
| 加速度計でわかる動物の動き | 14 | |
| バイオロギングからわかった動物行動の一般法則 | 17 | |
| 標本の世界 | マッコウクジラからもらった大型イカ類標本 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第2回 | 花と鳥の共進化 | 22 |
| 共生植物図鑑(2)キバナアキギリ | 25 | |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #25日本が世界にほこる技!? いろいろな「祈り」に挑戦! | 26 |
| かたちと科学 第5回 |
美しい原子配列のパターンを見せる準結晶 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2011年

2011年は世界化学年。マリー・キュリーが新元素ポロニウムやラジウムを発見し、ノーベル賞を授与されて100年目に当たります。表紙はこれまでに発見された元素が並ぶ周期表です。私たちの世界が、より安全で快適なものになっていくかどうかは、元素がもつ性質の解明と利用方法の研究にかかっています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | いち早く遺伝子研究に着目し、生体の情報伝達機構の秘密を解明 | 3 |
| 【特集】化学は世界を変えるか?-世界化学年に寄せて | 6 | |
| マリー・キュリー1911~2011 | 6 | |
| 人と環境にやさしい最新科学 | 10 | |
| 太陽光と水で水素をつくる | 13 | |
| 触媒と化学反応 | 16 | |
| 日本の化学研究の系譜:天然物化学の役割 | 18 | |
| 標本の世界 | 希少動物の寄生虫 | 20 |
| 共生・共進化する植物の世界 第1回 | 「植物」とは?-寡黙なる共生パートナー | 22 |
| 共生植物図鑑(1)アリ植物オオバギ属 | 25 | |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #24キッチンで楽しい化学実験! | 26 |
| かたちと科学 第4回 | 生物の模様は誰がデザインしたのか? | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

富士山4合目付近から撮影した9月5日17時半ごろの北西方向の空。まだ夏の太平洋高気圧に覆われ、湿った空気による雲海がひろがり、遠くには積乱雲がいくつも。上空には上層雲が流れてきて秋の気配。下界は曇りか弱い雨。中腹ならではの素晴らしい光景。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 新しいコンピュータの可能性 量子コンピュータの実現に向けて | 3 |
| 【特集】気象予測の科学-天気はどこまで予測できるのか?- | 6 | |
| 天気予報はいま~新たな予報、ナウキャスト~ | 6 | |
| 最新の気象予測システムが拓く気象ビジネス | 11 | |
| 気候変動予測の重要性とそれを可能にした大気海洋モデル | 14 | |
| 天気の変わり目に見られる雲 | 17 | |
| 標本の世界 | 天変地異の前兆!?希種サケガシラの標本 | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-最終回 | 深海のモンスター | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #23 雲のなぞをさぐろう | 26 |
| かたちと科学 第3回 | 「裏返しのシャボン玉」の不思議なふるまい | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

フクイサウルス(上)とフクイラプトル(下)。日本でもさまざまな恐竜の化石が発見されており、今後の研究により、アジアにおける恐竜の流入や分布などが明らかになっていくことが期待されています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 体内時計の解明がつなぐ、細胞内の活動と個体の生命現象 | 3 |
| 【特集】日本の恐竜 | 6 | |
| 日本の恐竜:30年にわたる発見・発掘と研究の進展 | 7 | |
| 発掘からみえてきた豊かな恐竜の群れ | 11 | |
| タンバリュウの全身骨格は発見されるか | 16 | |
| 日本で最初に発見された肉食恐竜化石“ミフネリュウ” | 19 | |
| ティタノサウルス形類の系譜 | 22 | |
| 標本の世界 | 明治時代の建築図面 | 24 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-第8回 | 深層流と気候変動 | 26 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #22 台所でできる!楽しい解ぼう教室 | 30 |
| かたちと科学 第2回 | 流体がつくり出す美しい渦 | 34 |
| NEWS & TOPICS | 36 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 38 |

表紙の写真は印刷がずれているわけではありません。赤青めがねで見ると立体的に見える「アナグリフ」です。赤青めがねの作りかたは、P.29をご覧ください。写っている昆虫は、オオススメバチ(上:東アジア、日本)とキバネツマルリタマムシ(下:タイ、マレーシアなど)です。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 新しい機能をもつ物質の発見から睡眠の謎へ | 3 |
| 【特集】いま、なぜ3Dか-見る能力、見せる技術- | 6 | |
| 3Dをよく知るために-ディスプレイ技術からみえてくる3D- | 6 | |
| 3Dのいま、むかし-写真の発展とともに歩んできた3D- | 11 | |
| ヒトの空間認識と脳 | 12 | |
| 3Dのあした-楽しむものから役に立つものへ- | 16 | |
| 医用画像の3次元可視化 | 17 | |
| 標本の世界 | 標本が語る海藻学の黎明期 | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-第7回 | 深海底の資源 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #21 ステレオスコープを作っておうちで3D体験! | 26 |
| かたちと科学 第1回 | プランクトンから宇宙ステーションへ | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

ヤモリはどうしてガラスの壁をのぼれるの? トンボはうすい翅(はね)で自由自在に飛べるのはなぜ? カタツムリの殻はなぜ汚れないの?
自然に秘められたしくみに学ぶ「ネイチャー・テクノロジー」が私たちの生活を変えるかもしれません。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 建築家のように分子をデザインし、新しい物質を生み出す有機合成化学 | 3 |
| 【特集】ネイチャー・テクノロジー-自然に学び技術をみがき、未来をつくる- | 6 | |
| ものつくりと暮らし方の新しい“かたち”-ネイチャー・テクノロジー | 6 | |
| 生物多様性がもたらす技術革新-「バイオミメティクス」 | 10 | |
| 自然史研究とバイオミメティクス | 13 | |
| トンボから学んだ風力発電 | 16 | |
| 自然に学ぶものづくり-企業がこれから取り組むこと | 18 | |
| 標本の世界 | 歴史的な医学資料にみる 西欧と日本 | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-第6回 | 「地球生命」誕生の物語 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #20 ルーペを持って小さな世界を探検しよう! | 26 |
| 科学技術の智を知る 最終回 | 科学技術のおもしろさ、豊かさを取り戻す | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

HRP-4C 未夢(左)とHRP-2。HRP-4C未夢はHRP-2の技術を継承しながら、外観寸法は日本人青年女性の身長、関節位置などの平均数値に一致するように開発された。人間にきわめて近い動作の実現をめざして現在も研究が進められている。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | アクチビンの発見が生物発生のしくみを解き明かす | 3 |
| 【特集】ヒューマノイド-ロボットはどこまで人間に近づいたのか- | 6 | |
| 外観(みかけ)の視点から-自分自身そっくりのジェミノイドとともに | 6 | |
| 動きの視点から-女性型ロボット「HRP-4C未夢」の与えたインパクト | 10 | |
| 社会とのかかわりのなかでわかってきたこと | 14 | |
| 人間を知り人間の役に立つためのヒューマノイド研究 | 17 | |
| 標本の世界 | クチバテングコウモリのタイプ標本 | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-第5回 | 深海に浮かぶ雲 | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #19 よく飛ぶ紙飛行機を作ろう | 26 |
| 科学技術の智を知る 第9回 | 技術と人間の関係をもう一度とらえ直す | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2010年

2010年4月に噴火したアイスランド南部・エイヤフィヤトラヨークトル火山。長期間にわたりヨーロッパの航空網を麻痺させたこの噴火はマグマと氷河から溶けた水が反応した「マグマ水蒸気爆発」で、飛び散った火山灰の大きさが非常に小さかったため、長期にわたり空中を漂い、その結果航空網に甚大な被害をもたらしたと考えられています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 脳の不思議をロボットで明らかにする | 3 |
| 【特集】火山を知る-火山学からみる地球の活動 | 6 | |
| 火山学はどのような学問か? | 6 | |
| 地球上のさまざまな火山 | 9 | |
| 火山とはなんだろう? | 12 | |
| 火山調査の醍醐味 | 14 | |
| 火山噴火の予知と防災 | 17 | |
| 標本の世界 | 幻のアザミ、スオウアザミ 二葉の標本が語る未知種の存在 | 20 |
| 深海-漆黒のフォロンティアを拓く-第4回 | 深海の熱水噴出にたむろする動物たち | 22 |
| 親子で学ぼう!科学冒険隊 | #18 つり合いの原理を利用してモビールを作ろう | 26 |
| 科学技術の智を語る 第8回 | 目に見えない「社会」を理解する | 30 |
| NEWS & TOPCS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
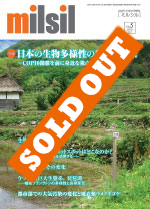
里山の原風景ともいえる棚田は、谷津田(谷地田)ともよばれ、山間の狭い地形に沿ってくつられる。森の中に開けた水面があることで、多様な生物の命が育まれている。写真は静岡県西伊豆の棚田。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 異文化から刺激が発見を導いた、好アルカリ性微生物の世界 | 3 |
| 【特集】日本の生物多様性の現状と未来~COP10開催を前に身近な視点から考える~ | 6 | |
| 生物の多様性とCOP10 | 6 | |
| 日本の生物多様性ホットスポットはどこなのか?-博物館の情報資源を活用する- | 9 | |
| 日本の里山とその変化 | 12 | |
| うつりゆく巨大生態系、琵琶湖
-植物プランクトンの多様性と長期変化- |
15 | |
| 都市部での大気汚染の変化と地衣類ウメノキゴケ | 18 | |
| 標本の世界 | 珪藻化石の個と群と | 20 |
| 深海-漆黒のフォロンティアを拓く-第3回 | 「深海」に生きる | 22 |
| 親子で学ぼう!科学冒険隊 | #17 ふしぎなシャボン玉作りに挑戦しよう! | 26 |
| 科学技術の智を語る 第7回 | ほかの生物を鏡に、人間の本質を見つめる | 30 |
| NEWS & TOPCS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

オーロラ帯の下にある昭和基地では、さまざまなオーロラが見られます。2009年9月14日3時すぎ、珍しく全天に広がり、オーロラの光で昭和基地周辺が見えてきました。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 脳機能の解明に大きな道を開いたfMRI | 3 |
| 【特集】南極-地球環境の変動を探る | 6 | |
| 地球温暖化の視点から見た南極の役割 | 6 | |
| 海洋深層循環を駆動する南極底層水
-未知の底層水生成域を探る- |
9 | |
| 南極の氷が明かす地球の気候変動 | 12 | |
| ペンギンからみる南極の環境変化 | 15 | |
| 大型大気レーダーで夜光雲の科学に挑む | 18 | |
| 標本の世界 | 万年時計の魅力 | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く-第2回 | 深海探査に挑む | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #16 磯の動物を観察しよう! | 26 |
| 科学技術の智を語る 第6回 | 数学の本質を知り、理解を深める | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
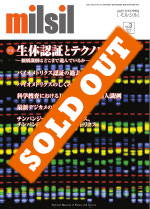
DNA解析イメージ。試料からDNAを抽出し、これを増幅、分離して、特有の識別バンドを検出・比較することにより、種や個体、類縁関係などを固定できるとされている。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 量子力学の理論を実証したホログラフィー電子顕微鏡 | 3 |
| 【特集】生体認証とテクノロジー -個別識別はどこまで進んでいるのか- | 6 | |
| バイオメトリクス認証の過去・現在 | 7 | |
| バイオメトリクスのしくみとセキュリティ | 10 | |
| 科学捜査におけるDNAを利用した個人識別 | 13 | |
| 最新デジカメの顔認識 | 16 | |
| チンパンジーのバイオメトリクス、チンパンジーによるバイオメトリクス | 17 | |
| 標本の世界 | 古い標本は役に立つ | 20 |
| 深海-漆黒のフロンティアを拓く- 第1回 | 「深海」とは何か? | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #15 万華鏡を作って、光の性質にふれよう! | 26 |
| 科学技術の智を知る 第5回 | 情報処理技術の根本のしくみとは | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

子育てをするベニクラゲ(めす)。北日本産のベイクラゲは南日本産より数倍大きく(直径1cm程度)、口柄が鮮やかな紅色です。球形の白い粒は未受精卵。めすは口柄でプラヌラ(幼生)を保育します(南日本産が産みっぱなしなのと対照的)。傘縁に多数の触手が数段あり、触手基部の紅色の目で光を感じて遊泳します。
| サイエンスインタビュー 科学のいま、そして未来 | ありふれたものから、社会に役立つ新機能素材をつくる材料科学 | 3 |
| 【特集】寿命-ここまでわかった!そのメカニズム | 6 | |
| 寿命は進化の産物-ゾウリムシの研究から | 7 | |
| 生物の長寿記録 | 10 | |
| 植物の寿命と動物の寿命 | 12 | |
| 不老不死のベニクラゲの神秘と人類の夢 | 15 | |
| カロリー制限による寿命管理 | 18 | |
| 標本の世界 | ビカリア | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして-生物多様性を考える-第8回 | 持続的な利用可能性と保全の取り組み | 22 |
| 連載をふり返って-生物多様性と私たちの未来 | 25 | |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #14 身近な鳥を観察しよう! | 26 |
| 科学技術の智を語る 第4回 | 物質への理解が私たちにもたらすもの | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

【特集】加速器とは何か、何がわかるか ─素粒子の謎を解き明かす最高性能の加速器─
スイスとフランスの国境にまたがる世界最大の加速器LHCでは、宇宙創造の鍵を握るといわれる素粒子を探査する壮大な実験が日本を含む世界各国の共同で行われています。写真は、地下100mにある実験施設の一つ、ATLAS測定器(建設時のもの)。
| サイエンスインタビュー 科学のいま、そして未来 | 複雑な現象を解きほぐす複雑系の数理モデル学 | 3 |
| 【特集】加速器とは何か、何がわかるか -素粒子の鍵を解き明かす最高性能の加速器- | 6 | |
| 素粒子の世界を拓く加速器 | 7 | |
| 日本と世界を代表する加速器 | 10 | |
| 素粒子と宇宙 その密接な関係 | 12 | |
| ビック粒子を探す -LHCで質量の起源を探る | 15 | |
| 日本の素粒子物理学と加速器の実験 | 18 | |
| 標本の世界 | 地衣類標本から抽出される化学成分 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える-第7回 | なぜ外来生物は増え続けるのか? | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #13 ペットボトルで、雲や雪の結晶を作ろう | 26 |
| 科学技術の智を語る 第3回 | 生物とは何か、そしてヒトとは何かを考える | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2009年
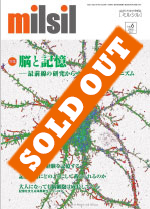
写真は海馬神経細胞(蛍光染色したもの)。中心の細胞体から柔突起幹が全体に伸びています。たくさんのやわらかな棘のように見えるのが樹状突起フィロポディア。樹状突起フィロポディアはシナプスの前駆体です。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 日本初の新材料 カーボンナノチューブ発見の道のり | 3 |
| 【特集】脳と記憶 -最前線の研究からせまる記憶のメカニズム | 6 | |
| 記憶と神経細胞 | 7 | |
| 脳はリズムで経験を記憶する | 11 | |
| 機能は脳にどのようにして蓄えられるのか | 14 | |
| 大人になっても脳細胞は成長している | 17 | |
| 標本の世界 | 大都市「江戸」の裏側 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える-第6回 | 生存する多様な生物とその価値 | 22 |
| 親子で学ぼう!科学冒険隊 | #12 タネの模型を飛ばしてみよう | 26 |
| 科学技術の智を語る 第2回 | リンクする宇宙の謎と地球科学の謎 | 30 |
| NEWS & TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

ジャワ原人は、最近の研究によると、インドネシアで100万年以上もの長い間、独自の進化を遂げたことがわかってきました。また、ほぼ同年代に生きていた北京原人との交流はほとんどなかったと考えられています。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | DNAの不連続複製のしくみを解明し、染色体の複製機構に挑む | 3 |
| 【特集】人類進化-新たな謎 | 6 | |
| 人類進化の系統樹 | 7 | |
| 最初の人類を求めて | 9 | |
| 絶滅した人類のなかまたち | 12 | |
| アフリカを出た最初の人類 | 14 | |
| ホモ・フロレシエンシスの発見と謎 | 16 | |
| ネアンデルタール人の謎 | 18 | |
| 標本の世界 | フタバスズキオリュウと記載論文 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える-第5回 | 遺伝子の多様性理解する~"進化は善である"という視点~ | 22 |
| 親子で学ぼう!科学冒険隊 | #11 色画用紙やペットボトルで地震を知ろう | 26 |
| 科学技術の智を語る 第1回 | 21世紀の科学技術リテラシーとは何か | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

多くの昆虫はヒトには見えない紫外線を感知する能力があることが知られています。モンシロチョウのめすの翅はこの紫外線で見るとわかる「紫外色」の衣装をまとい、おすはこの色をめざしてやってきます。昆虫はさまざまな形で光と色を巧みに利用して生きているのです。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 関節リウマチ治療に革命を起こしたインターロイキン6の研究を探る | 3 |
| 【特集】光と色を利用する昆虫たち | 6 | |
| 昆虫の色とその魅力 | 7 | |
| タマムシ | 10 | |
| 「まぼろし色」のチョウを追い求めて | 13 | |
| 太陽を利用するミツバチの秘密 | 16 | |
| チョウに色は見えるのか? | 16 | |
| 標本の世界 | 地上から消えた植物の標本 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える- 第4回 | サンゴ礁の生物多様性 サンゴがはぐくむ生き物たち | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #10 もどってくる、ブーメランのふしぎ | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第10回 | サイエンスコミュニケーションのこれから | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

電子顕微鏡写真をもとに作成したウイルスの図。構造の異なるさまざまな形のウイルスが見られる。細菌より小さく、その発見は困難をきわめた。背景の写真はインフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真。ウイルス発見の歴史、ウイルスの分類については特集ページをご覧下さい。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | さまざまな角度からの証拠を集め暗黒物質(ダークマター)の正体に迫る | 3 |
| 【特集】ウイルス-その多様性と謎に満ちた存在- | 6 | |
| 目に見えない敵と闘った者たち | 7 | |
| ウイルス学とノーベル賞 | 11 | |
| what's Virus? -ウイルスって何? | 12 | |
| ウイルスハンター | 16 | |
| 標本の世界 | 塩原の木の葉石 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える- 第3回 | 熱帯雨林に見る生物多様性とその価値 | 22 |
| 生物多様性ホットスポットの役割とは | 25 | |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #09 アニメーションの不思議を知ろう | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第9回 | コミュニケーションの担い手を育てる | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

史上最大級の肉食恐竜として人気の高いティラノサウルス。写真の骨格標本は、骨格の大部分が発掘され「スタン」と名付けられた個体のレプリカ(国立科学博物館に常設展示)。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 原子・分子の制御で社会に役立つ材料科学研究を探る | 3 |
| 【特集】恐竜学のいま | 6 | |
| 恐竜学の歴史、そしていまどこまで進んだのか? | 7 | |
| 恐竜たちのいま・むかし | 10 | |
| 恐竜進化の読み解き方 | 12 | |
| 恐竜を最先端のテクノロジーで探る | 15 | |
| なぜ恐竜は絶滅したのか? | 18 | |
| 標本の世界 | 青い花の色が発現するしくみの解明 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える- 第2回 | 地球上に生物は何種類いるのだろうか | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #08 恐竜展示をもっと楽しく探検しよう! | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第8回 | 科学の不思議を五感でとらえる 臨場感が魅力のサイエンスショー | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

光学望遠鏡で観測したアンドロメダ銀河(M31)。アンドロメダ座のうずまき銀河で、わたしたちの住む銀河系(天の川銀河)よりも大きい。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 地震災害を最小限にとどめるためのリアルタイム地震学 | 3 |
| 【特集】世界天文年2009 | 6 | |
| <第一部> | すべてはガリレオの望遠鏡から始まった | 7 |
| 見えなかった宇宙から何が見えてくるのか | 10 | |
| <第二部> | いかにして系外惑星を発見するか | 12 |
| 電波で宇宙を見る | 16 | |
| 標本の世界 | フランス人宣教師フォーリーの遺した標本 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして -生物多様性を考える- 第1回 | 生物多様性と共生する | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #07 身近なもので望遠鏡を作ろう | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第7回 | サイエンスフェスティバルの試み | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
2008年

【特集】身近で謎に満ちた生物・菌類 ─最新科学技術から見る菌類の世界─
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | ナノテクノロジーによって革新的機能の新材料をつくり出す | 3 |
| 【特集】身近で謎に満ちた生物・菌類-最新科学技術から見る菌類の世界- | 6 | |
| 知られざる菌類の世界 | 7 | |
| アオカビが世界を変えた | 11 | |
| 黄麹菌のゲノム解析からわかった新事実 | 15 | |
| ホンシメジの人工栽培からわかったマツタケ人工栽培の可能性 | 18 | |
| 標本の世界 | ヤンバルテナガコガネのタイプ標本 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第6回 | 人類は、どこに向かって進んでいくのだろう?サスティナブルな社会の実現をめざして | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #06 発酵を体験しよう! | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第6回 | 科学の不思議を五感でとらえる 臨場感が魅力のサイエンスショー | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
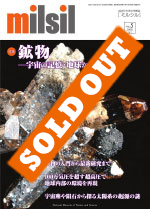
トパーズは、宝石としても古くからよく知られる鉱物のひとつ。ケイ酸塩鉱物で、和名は黄玉(おうぎょく)という。透明や橙色などさまざまな色があるが、宝石としては褐色のものが上質とされる。表紙写真はトパーズ原石、アメリカ産。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 最先端のイメージング技術で免疫というシステムの全体像に迫る | 3 |
| 【特集】鉱物 ―宇宙の記憶・地球からの贈り物― | 6 | |
| 鉱物の入門から最新研究まで | 7 | |
| 100万気圧を超す超高圧で地球内部の環境を再現 | 11 | |
| 宇宙塵や隕石から探る太陽系の起源の謎 | 15 | |
| 標本の世界 | 地震学の父の残したもの | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第5回 | 高自給率、高効率のエネルギー政策をめざして | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #05 スイーツ de 火山学! | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第5回 | 英国サイエンスコミュニケーション事情 | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
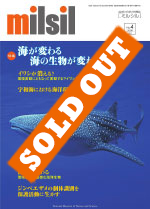
ジンベエザメは世界最大の魚類だが、性格は極めておとなしい。「フカヒレ」の材料としては最高級といわれ大量に漁獲されてきたが、現在では国際自然保護連合(IUCN)の「レッドリスト」で「絶滅危惧種」に指定されている。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | コミュニケーションを脳科学で解明する | 3 |
| 【特集】海が変わる 海の生物が変わる | イワシが消える? | 7 |
| 宇和海における海洋環境の長期観測 | 11 | |
| 海岸が変わる | 14 | |
| ジンベエザメの個体識別を保護活動に生かす | 17 | |
| 標本の世界 | トガクシソウ | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第4回 | 温暖化回避と豊かな生活の両立をめざす | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #04 デジカメで昆虫撮影に挑戦 | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第4回 | 科学と芸術の融合をめざして | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

みごとなハナカマキリの擬態。しかし、人間の脳は視覚の情報に実際には見えない輪郭を補うことで、ハナカマキリの姿を識別することができます。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 万能細胞「iPS細胞」で再生医療実用化が大きく前進 | 3 |
| 【特集】見る―視覚と脳のふしぎな関係 | 錯覚の世界 | 6 |
| 世界は脳でつくられる | 10 | |
| 脳をだます | 14 | |
| テレビ開発に大きな役割を果たした視覚の研究 | 18 | |
| 標本の世界 | 小さな博物館の大きなコレクション | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第3回 | 二酸化炭素を切り口に、地球環境の今後をさぐる | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #03 トリックアートを体験する | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第3回 | 科学者よ街に出て、みんなと語ろう | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |
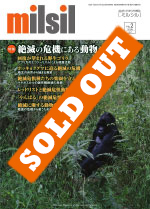
世界全体全体をあわせても、野生のゴリラの生息数は現在3000~5000頭とされ、いまも絶滅が心配されている。
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | ロボットで解き明かす人間のミステリー | 3 |
| 【特集】絶滅の危機にある動物たち | 回復が望まれる野生ゴリラ | 7 |
| ホッキョクグマに迫る絶滅の危機 | 9 | |
| 絶滅危惧種たちの楽園を守る | 10 | |
| レッドリストと絶滅危惧動物 | 12 | |
| 「やんばる」絶滅危惧動物とマングース | 14 | |
| 絶滅に瀕する動物を、再び野生に! | 18 | |
| 標本の世界 | 日本最古の『クモの標本』 | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第2回 | 温暖化で地球の未来はどうなるのか? | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学探検隊 | #02 大気圧を体験する | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第2回 | イギリスから始まり、世界に広がったサイエンスカフェの流儀 | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milshilカフェ/編集後記/定期購読のお知らせ/次号予告 | 34 |

世界でただ1種、海に潜って海藻を食べるウミイグアナは、体が冷えると日光浴をして体を温めます。
| 創刊にあたって | 科学を文化に 国立科学博物館長 佐々木正峰 | 3 |
| サイエンス・インタビュー 科学のいま、そして未来 | 地底での素粒子研究から宇宙の謎に迫る | 4 |
| 【特集】進化<第一部> | ダーウィン・生物の進化をめぐる旅 | 6 |
| 【特集】進化<第二部> | ガラパゴスのいま | 14 |
| 6人の研究者たち | 16 | |
| 標本の世界 | 謎の巨大魚 マンボウ | 20 |
| 人類と自然の共存をめざして 第1回 | 地球温暖化は、本当に起きているのだろうか? | 22 |
| 親子で遊ぼう!科学冒険隊 | #01 光でアートする | 26 |
| サイエンスコミュニケーションへの招待 第1回 | サイエンスコミュニケーションとは何か? | 30 |
| NEWS&TOPICS | 32 | |
| milsilカフェ/編集後記/次号予告 | 34 |