花崗岩質大陸のできかたを明らかにする

谷 健一郎(たに けんいちろう)
理学研究部
鉱物化学研究グループ
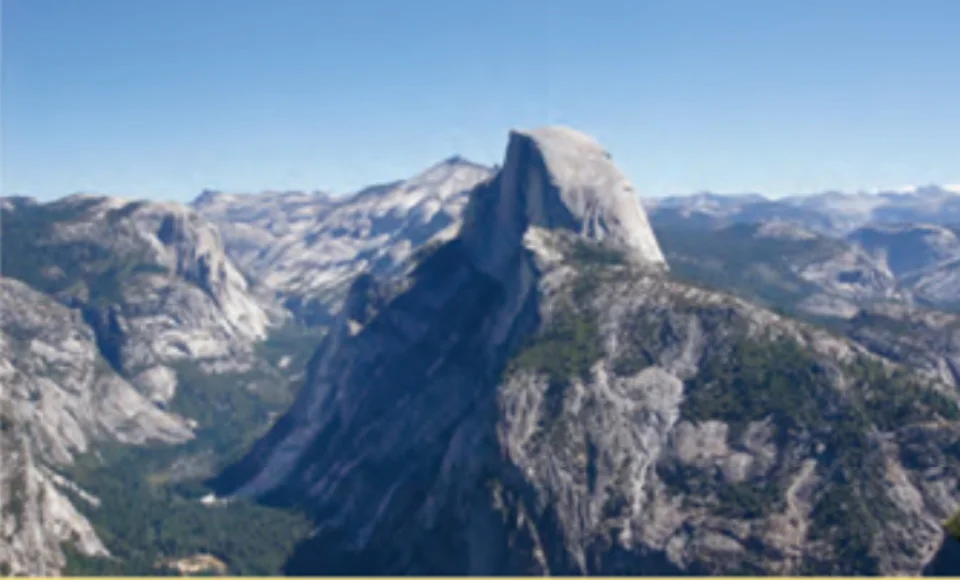 アメリカ合衆国西部のヨセミテ国立公園:見渡す限り中生代の花崗岩が露出している。大陸地殻の大部分は花崗岩と花崗岩起源の堆積岩・変成岩で構成される
アメリカ合衆国西部のヨセミテ国立公園:見渡す限り中生代の花崗岩が露出している。大陸地殻の大部分は花崗岩と花崗岩起源の堆積岩・変成岩で構成される我々人類が暮らしている陸地は主に花崗岩から形成される大陸地殻から成ります。花崗岩は太陽系惑星のなかでも地球にしか存在しない不思議な岩石で、花崗岩質の大陸地殻が地球の46億年の歴史のなかで、どこで生まれ、どのようにして現在のような姿にまで成長してきたのかは依然としてよくわかっていません。
一つの仮説として、大陸地殻を作る花崗岩質マグマは、海洋プレートが別のプレートの下に沈み込んでいく島弧という場所で大量に出来るのではないかと考えられています。そしてそのようなプロセスが現在も起こっている可能性が高いのが、日本の伊豆諸島なのです。伊豆諸島は伊豆小笠原弧と呼ばれる島弧の一部で、海底の下では今も花崗岩質の大陸地殻が生まれていると考えられています。
私は海洋調査船や有人潜水船「しんかい6500」・無人探査機などを使った海底調査を行って、伊豆小笠原弧の地下に存在するはずの花崗岩を探してきました。
その結果、2007年に伊豆諸島八丈島の西方海域において、世界で初めて丸ごと花崗岩で出来た海山を発見しました。ジルコン・ウラン‐鉛年代測定法という手法を使ってこの花崗岩海山が出来た年代を調べたところ、今から260万年前だと判りました。これは地質学的には非常に若い、できたてホヤホヤの花崗岩です。
私は野外調査から読み取れる地質学的情報と実験室で様々な機器を使って分析することで得られる岩石学・年代学・地球化学的情報を組み合わせることで、花崗岩を作ったマグマがいつ、どのように、どれくらい、出来るのかを調べています。それによって太陽系で地球にしかない岩石、花崗岩の成因を明らかにすることを目指しています。
 無人探査機「ハイパードルフィン3000」
無人探査機「ハイパードルフィン3000」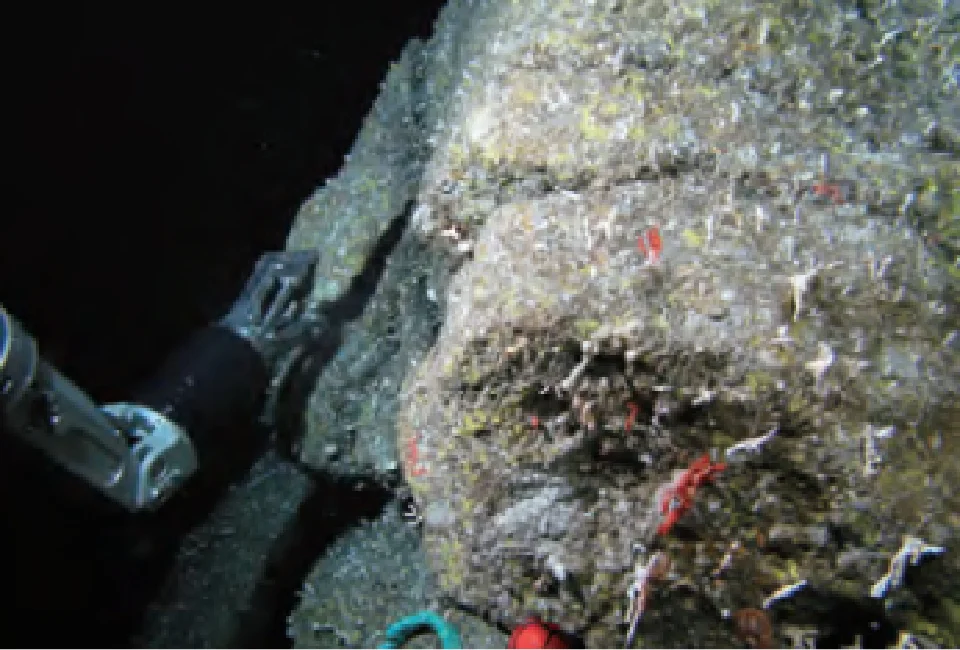 八丈島西方海域の第三西スミス海丘で発見された花崗岩の露頭(水深約 600m)
八丈島西方海域の第三西スミス海丘で発見された花崗岩の露頭(水深約 600m)研究員に聞いてみました

1)専門は何ですか?
地質学のなかでも岩石学と年代学という分野が専門です。大陸地殻や火山を作るマグ マがいつ、どのようにして出来るのかを研究しています。
2)研究者になろうと思ったきっかけは?
登山や探検が好きで高校の時から山岳部に入っていました。大学でも研究という名目 で山に行けそうな学科ということで地質学を選んでしまい、今に至ります。
3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?
今年の春に調査を行っていたフィリピンの小さな島で、たまたま海岸で目について拾った一個の石ころがきっかけとなって、ジャン グルの山奥で特殊なマグマを噴出するこれまで知られていなかった火山を発見しまし た。猛毒のコブラに怯えながら現地の人も立ち入らない未開のヤブをかき分けて進んでいくと突然巨大な溶岩流が出現し、思わず歓声を上げてしまいました。
4)研究者になりたい方に一言アドバイスを!
自然科学系の研究者生活は意外と(?)肉体労働の日々です。まずは体力と気 力をつけましょう。