有楽町で骨に会いましょう
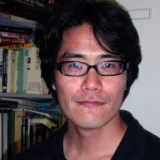
坂上 和弘(さかうえ かずひろ)
生命史研究部
人類史研究グループ

2013年、千代田区の有楽町一丁目(宝塚劇場近く)から、6個体の室町 時代人骨が発見されました。当時の現場は入り江(日比谷入江)の中で、5個体が一直線状に並び、西を向いた状態で埋葬されていたようです。

手のひらを太陽に(向けない)
この内、人骨番号171号(7歳前後)は両手を杭で貫かれた状態で出土しました。手の骨を詳細に調べると、左手を右手の甲に乗せた不自然な状態(下図参考)のため、誰かが何らかの意図を持って刺した可能性が高いと思われます。入り江の中で体重の軽い子供を「西に向かせ続ける」ためだったのかもしれません。


(もちろん)骨まで愛して
このように、人骨は、その持ち主の個性だけではなく、「ご遺体をどう扱ったか」といった、当時の人たちの考え方や価値観を教えてくれます。「遺体」でありながら、「文化財」でもある人骨の魅力、自然人類学者が骨を愛してやまない理由をご理解いただければ幸いです。
研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか
自然人類学が専門で、細分化すると、形態人類学、法医人類学です。
2 )自身の研究内容と社会、一般との接点は
考古学の現場で発掘された人骨の鑑定や調査を行い、昔の人がどのような人々だった のかを明らかにしています。また、たまに殺人事件を解決したりしています。
3)やりがいを感じるのはどのようなときですか
骨から読み取った情報が真実であったこと が 判 明したときで す。「謎 はすべて解け た!」。間違えた時は耳から手を突っ込んで奥歯を引っこ抜きたくなりますが ……。
4)研究する上での苦労や悩みなどはありますか
大部分の人に気持ち悪がられることと、それによって家族が被害を受けたことです。