| Date: Thu, 11 Sep 2002 22:12:23 +0900 Subject: Re:俳句天体運行図 From: 館長 To: 俳句好きの日本画家 |
|
| むかし詠まれた歌のなかに注目すべき天文現象が隠れていることがあるそうじゃが、この蕪村の句も研究者たちによっていつどこで詠まれたのかということが特定されておるそうじゃ。さて絵じゃが、たしかに「月は東に日は西に」という位置関係は見事に再現されておる。しかし、月の満ち欠けは太陽光がつくる月面上の日なたの部分と日かげの部分が地球上からどのように見えるかで決まることを忘れておるようなじゃのう。芸術家といえども絵にとりかかる前に太陽・地球・月の位置関係をよく確かめてもらいたいものじゃ。 ◆こたえ 日没時、同時に昇ってくる月は必ず満月であり、三日月はありえない。 ◆解説 月の満ち欠けを考えることはとても面白い。月も地球と同様、常に太陽からの光を受けている。つまり月の半分は必ず日なた、もう半分は日陰になっている。その姿を地球から見ると位置関係によって見え方が変わり、満ち欠けしているように見えるのである。太陽、地球、月が一直線上に並ぶと、地球の影が月の表面に落ちて月食が起こる。これは特別な場合で、月の満ち欠けとは直接関係はない。ちなみに蕪村の「菜の花や月は東に日は西に」という句は、月と日の位置関係から詠んだ場所と時間が特定されている。 |
|
| 菜の花や月は東に日は西に | |
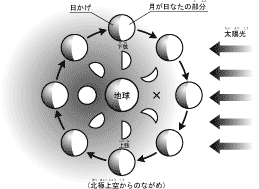 |